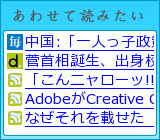自宅でDVD三昧!~映画・ドラマどんと来い!
もちろん映画館で見る大画面の映画の雰囲気は最高。でも自宅でまったりDVD三昧というのも良い物だ。人目を気にせず見た映画DVD・ドラマDVDの感想など書き散らしてみたり。
« 2006年09月06日 | メイン | 2006年09月16日 »
2006年09月13日
シビル・ガン 楽園をください
南北戦争下、カンザス州とミズーリ州の州境の森に、南軍のゲリラがキャンプを張っていた。
18歳のジェイク(トビー・マグワイア)は、黒人のホルトを含む4人のグループで行動していた。
銃撃戦の演出が素晴らしい。
旧式のピストルの発射音、壁やガラスを貫通する音、そして撃たれた者の倒れ方。これほどリアリティーのある銃撃戦は見たことがない。
また、数百人の南軍ゲリラと北軍の騎馬戦は圧巻だ。その疾走感は爽快で、思わず「いけ~!」と叫びそうになった。
戦闘シーンも見事だが、この映画はアクション映画ではない。
1861年のアメリカを忠実に再現している。誇張のない演出は、誠実というか、真摯というか、丹念に丹念に作られており、ハリウッド的なエンターテインメント性はいささかも感じられない。
それがまた独特の味わいを醸し出している。
北軍に包囲され、窮地に陥ったゲリラは、ローレンスという街を襲撃し、すべての男性を北軍とみなして虐殺する。
これは実話であり、殺された男性は、兵士でも北軍でもなかった。
ジェイクとホルトは、狂った仲間たちを見ながら、殺戮には手を貸さなかった。
戦争という狂気は、人間の善性を麻痺させる。そこでは、まったく無意味で陰惨な殺戮が繰り返される。いかに戦争が愚かなことか、映画は痛切に訴えてくる。
また、ホルトが慕う主人ジョージが死に、ホルトは悲しみにくれるのだが、ホルトは初めて「自由」を感じる。南北戦争の争点であった奴隷制度が、どれほど黒人の心を縛り、苦しめていたのか。さまざまなシーンで描かれている。
こんな正統派な映画は見たことがない。
なんのてらいもなく、男の友情や人を許すこと、家族愛が描かれる。それなのにクサくない。それほどに完成度が高いのだ。
18歳のジェイク(トビー・マグワイア)は、黒人のホルトを含む4人のグループで行動していた。
銃撃戦の演出が素晴らしい。
旧式のピストルの発射音、壁やガラスを貫通する音、そして撃たれた者の倒れ方。これほどリアリティーのある銃撃戦は見たことがない。
また、数百人の南軍ゲリラと北軍の騎馬戦は圧巻だ。その疾走感は爽快で、思わず「いけ~!」と叫びそうになった。
戦闘シーンも見事だが、この映画はアクション映画ではない。
1861年のアメリカを忠実に再現している。誇張のない演出は、誠実というか、真摯というか、丹念に丹念に作られており、ハリウッド的なエンターテインメント性はいささかも感じられない。
それがまた独特の味わいを醸し出している。
北軍に包囲され、窮地に陥ったゲリラは、ローレンスという街を襲撃し、すべての男性を北軍とみなして虐殺する。
これは実話であり、殺された男性は、兵士でも北軍でもなかった。
ジェイクとホルトは、狂った仲間たちを見ながら、殺戮には手を貸さなかった。
戦争という狂気は、人間の善性を麻痺させる。そこでは、まったく無意味で陰惨な殺戮が繰り返される。いかに戦争が愚かなことか、映画は痛切に訴えてくる。
また、ホルトが慕う主人ジョージが死に、ホルトは悲しみにくれるのだが、ホルトは初めて「自由」を感じる。南北戦争の争点であった奴隷制度が、どれほど黒人の心を縛り、苦しめていたのか。さまざまなシーンで描かれている。
こんな正統派な映画は見たことがない。
なんのてらいもなく、男の友情や人を許すこと、家族愛が描かれる。それなのにクサくない。それほどに完成度が高いのだ。
- 最近のエントリー
-
[
 新着情報]
新着情報]
- カテゴリー
- 検索
- 最近のコメント
-
- 十五才 学校IV
- └ click the next website 11/28
- └ roxy 11/30
- └ kubah mesjid enamel 01/29
- └ timberland earthkeepers fit 12/04
- └ gucci 2014 boxing day 2014 12/18
- └ kedged.rcbrevisions.com/disarm/centum.html 04/12
- └ Men's Air Max 87 12/17
- └ Nike Shox Deliver Scarpe 12/19
- └ read this 09/08
- 十五才 学校IV
- 最近のトラックバック
-
-
バーティカル・リミット
- vimax asli
- »vimax asli
- 05/06 06:47
- christian louboutin sales
- »christian louboutin sales
- 11/25 11:55
- 11/23 12:56
- buying academic essays
- »shahpourco.com
- 05/06 05:35
- Homes for sale Bethesda Maryland
- »gear.gp
- 05/06 04:49
- hcg drops
- »www.hcgdropsshop.com
- 05/06 04:46
- baby potty training
- »baby potty training
- 05/02 13:46
- small fly swatter
- »small fly swatter
- 04/27 16:27
- Search Engine Optimization
- »Search Engine Optimization
- 04/25 03:11
-
バーティカル・リミット
- ブログ・アクセサリー
-
-

track feed -
-
-