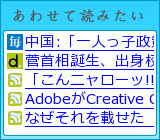自宅でDVD三昧!~映画・ドラマどんと来い!
もちろん映画館で見る大画面の映画の雰囲気は最高。でも自宅でまったりDVD三昧というのも良い物だ。人目を気にせず見た映画DVD・ドラマDVDの感想など書き散らしてみたり。
« 2006年08月 | メイン | 2006年10月 »
2006年09月29日
バガー・ヴァンスの伝説
バガー・ヴァンスとは、ウィル・スミス扮する謎めいたキャディーの名前であり、彼の存在によって全体がおとぎ話のような雰囲気になっている。
物語の中心は、第一次大戦で心に傷を負い、栄光のゴルファーから博徒に身をやつしていたジュナ(マット・デイモン)の再起をバガーが助けるというもの。
また、ジュナのかつての恋人で富豪の娘アデールが、恐慌による破産状態からゴルフ場経営を再建させる。そして、ジュナを慕う少年ハーディの父も仕事を失った。
登場人物たちは、社会の荒波にもまれ、奈落の底にいるが、バガーによって救われていくのだ。
この映画のキーワードは「自分らしさ」。
12年間、博徒の生活を送ったジュナは、自分のスイングを失っていた。バガーは「ゴルフのグリップは人生のグリップ。自分のスイングを見つけろ」とアドバイスする。
人間は、とかく人と自分を比べがちだ。
華やかな人をうらやみ、背伸びしようとする。ないものねだりをする。
いつまでそうしていても、ないものは出てこない。自分のもっているもので勝負するしかないのだ。
人と比べるのではなく、自分らしい生き方こそ、人を幸福にする。
現代には、浮かれた成功者があふれている。そんな成功者に憧れ、夢見る人がいる。
この映画は「自分らしく生きること」こそ、幸福の極意だと教えてくれる。
物語の中心は、第一次大戦で心に傷を負い、栄光のゴルファーから博徒に身をやつしていたジュナ(マット・デイモン)の再起をバガーが助けるというもの。
また、ジュナのかつての恋人で富豪の娘アデールが、恐慌による破産状態からゴルフ場経営を再建させる。そして、ジュナを慕う少年ハーディの父も仕事を失った。
登場人物たちは、社会の荒波にもまれ、奈落の底にいるが、バガーによって救われていくのだ。
この映画のキーワードは「自分らしさ」。
12年間、博徒の生活を送ったジュナは、自分のスイングを失っていた。バガーは「ゴルフのグリップは人生のグリップ。自分のスイングを見つけろ」とアドバイスする。
人間は、とかく人と自分を比べがちだ。
華やかな人をうらやみ、背伸びしようとする。ないものねだりをする。
いつまでそうしていても、ないものは出てこない。自分のもっているもので勝負するしかないのだ。
人と比べるのではなく、自分らしい生き方こそ、人を幸福にする。
現代には、浮かれた成功者があふれている。そんな成功者に憧れ、夢見る人がいる。
この映画は「自分らしく生きること」こそ、幸福の極意だと教えてくれる。
2006年09月26日
ベロニカは死ぬことにした
この映画の原作は、パウロ・コエーリョの同名小説「ベロニカは死ぬことにした 」。
」。
既に世界120カ国以上で翻訳され、日本語版でも20万部を超す話題作らしい。
一見、満ち足りた生活を送る、ある若い女性の絶望と再生の物語。その舞台を、7年連続して3万人の自殺者が出ている日本に置き換えて、映画化した。
「なんでもあるけど、なんにもない」退屈な人生にうんざりして、自らの命を絶とうとした28歳のトワ(真木よう子)が目覚めた場所は、ちょっと変わったサナトリウム。「君はあと7日間の命だ」と、院長(市村正親)が宣告する。
自分に残されたあまりに短い時間を送るうち、はじめて彼女は、それまで拒絶していた自分自身を受け入れ、周囲に目を向ける。
おいしいものを食べること、楽しむこと、好きな格好をすること、美しい音楽を奏でる喜び、人生を彩るものすべてが彼女を変えていき、率直な生への欲求が芽生え始める……。
院内での風変わりな人々の独特な世界と、ファンタジーな映像で、一風変わった浮遊感のある作品になっている。
風吹ジュン、中嶋朋子、荻野目慶子、淡路恵子のほかに、韓国の人気俳優イ・ワンや、NHKの子ども番組で人気のミュージシャン・山口トモなど、異色の配役も楽しい。
多彩な役者陣のなかで、若手女優・真木よう子がヒロイン・トワを演じ、その演技で作品を引き締めている。
現代人、中でも女性たちが抱える生きにくさを見すえながら、どこかふわりとしたさわやかさで、ラストがまた感動的な瞬間となっている。
既に世界120カ国以上で翻訳され、日本語版でも20万部を超す話題作らしい。
一見、満ち足りた生活を送る、ある若い女性の絶望と再生の物語。その舞台を、7年連続して3万人の自殺者が出ている日本に置き換えて、映画化した。
「なんでもあるけど、なんにもない」退屈な人生にうんざりして、自らの命を絶とうとした28歳のトワ(真木よう子)が目覚めた場所は、ちょっと変わったサナトリウム。「君はあと7日間の命だ」と、院長(市村正親)が宣告する。
自分に残されたあまりに短い時間を送るうち、はじめて彼女は、それまで拒絶していた自分自身を受け入れ、周囲に目を向ける。
おいしいものを食べること、楽しむこと、好きな格好をすること、美しい音楽を奏でる喜び、人生を彩るものすべてが彼女を変えていき、率直な生への欲求が芽生え始める……。
院内での風変わりな人々の独特な世界と、ファンタジーな映像で、一風変わった浮遊感のある作品になっている。
風吹ジュン、中嶋朋子、荻野目慶子、淡路恵子のほかに、韓国の人気俳優イ・ワンや、NHKの子ども番組で人気のミュージシャン・山口トモなど、異色の配役も楽しい。
多彩な役者陣のなかで、若手女優・真木よう子がヒロイン・トワを演じ、その演技で作品を引き締めている。
現代人、中でも女性たちが抱える生きにくさを見すえながら、どこかふわりとしたさわやかさで、ラストがまた感動的な瞬間となっている。
2006年09月16日
アンブレイカブル
「シックス・センス」が世界的に大ヒットを記録したM・ナイト・シャマラン監督。
彼の強みは独創的な脚本にあると思う。
シャマランの映画がもたらす驚きは大仰な視覚効果ではなく、巧妙に設計された物語による。「シックス・センス」でも全く意表をついた結末を準備して、あっと言わせてくれた。
悲惨な列車衝突事故で物語は幕を開ける。
乗客・乗員132人の内、131人までが死亡。たった1人の生存者デヴィッド・ダン(ブルース・ウィリス)は何と全くの無傷だった。
その日から彼に接近し始めた漫画コレクター、イライジャ・プライス(サミュエル・L・ジャクソン)はダンに質問する。
「あなたはこれまでに何回病気をしたことがあるか?」と。
次第に明らかになるのは、ダンが“決して壊れない(アンブレイカブルな)肉体”の持ち主であるということ。
そして一方、プライスはといえば、子どもの頃からケガが絶えない体だった。
物語はいかにもシャマランの映画らしく、その後も予想のつかない意外な展開を見せる。
さらに今回はなかなかの漫画オタクぶりも垣間見せるシャマラン。
メディア・ミックス的な卓越した想像力が、誰が見ても楽しめるエンターテインメント性と見事に共存している点がすごい。
彼の強みは独創的な脚本にあると思う。
シャマランの映画がもたらす驚きは大仰な視覚効果ではなく、巧妙に設計された物語による。「シックス・センス」でも全く意表をついた結末を準備して、あっと言わせてくれた。
悲惨な列車衝突事故で物語は幕を開ける。
乗客・乗員132人の内、131人までが死亡。たった1人の生存者デヴィッド・ダン(ブルース・ウィリス)は何と全くの無傷だった。
その日から彼に接近し始めた漫画コレクター、イライジャ・プライス(サミュエル・L・ジャクソン)はダンに質問する。
「あなたはこれまでに何回病気をしたことがあるか?」と。
次第に明らかになるのは、ダンが“決して壊れない(アンブレイカブルな)肉体”の持ち主であるということ。
そして一方、プライスはといえば、子どもの頃からケガが絶えない体だった。
物語はいかにもシャマランの映画らしく、その後も予想のつかない意外な展開を見せる。
さらに今回はなかなかの漫画オタクぶりも垣間見せるシャマラン。
メディア・ミックス的な卓越した想像力が、誰が見ても楽しめるエンターテインメント性と見事に共存している点がすごい。
2006年09月13日
シビル・ガン 楽園をください
南北戦争下、カンザス州とミズーリ州の州境の森に、南軍のゲリラがキャンプを張っていた。
18歳のジェイク(トビー・マグワイア)は、黒人のホルトを含む4人のグループで行動していた。
銃撃戦の演出が素晴らしい。
旧式のピストルの発射音、壁やガラスを貫通する音、そして撃たれた者の倒れ方。これほどリアリティーのある銃撃戦は見たことがない。
また、数百人の南軍ゲリラと北軍の騎馬戦は圧巻だ。その疾走感は爽快で、思わず「いけ~!」と叫びそうになった。
戦闘シーンも見事だが、この映画はアクション映画ではない。
1861年のアメリカを忠実に再現している。誇張のない演出は、誠実というか、真摯というか、丹念に丹念に作られており、ハリウッド的なエンターテインメント性はいささかも感じられない。
それがまた独特の味わいを醸し出している。
北軍に包囲され、窮地に陥ったゲリラは、ローレンスという街を襲撃し、すべての男性を北軍とみなして虐殺する。
これは実話であり、殺された男性は、兵士でも北軍でもなかった。
ジェイクとホルトは、狂った仲間たちを見ながら、殺戮には手を貸さなかった。
戦争という狂気は、人間の善性を麻痺させる。そこでは、まったく無意味で陰惨な殺戮が繰り返される。いかに戦争が愚かなことか、映画は痛切に訴えてくる。
また、ホルトが慕う主人ジョージが死に、ホルトは悲しみにくれるのだが、ホルトは初めて「自由」を感じる。南北戦争の争点であった奴隷制度が、どれほど黒人の心を縛り、苦しめていたのか。さまざまなシーンで描かれている。
こんな正統派な映画は見たことがない。
なんのてらいもなく、男の友情や人を許すこと、家族愛が描かれる。それなのにクサくない。それほどに完成度が高いのだ。
18歳のジェイク(トビー・マグワイア)は、黒人のホルトを含む4人のグループで行動していた。
銃撃戦の演出が素晴らしい。
旧式のピストルの発射音、壁やガラスを貫通する音、そして撃たれた者の倒れ方。これほどリアリティーのある銃撃戦は見たことがない。
また、数百人の南軍ゲリラと北軍の騎馬戦は圧巻だ。その疾走感は爽快で、思わず「いけ~!」と叫びそうになった。
戦闘シーンも見事だが、この映画はアクション映画ではない。
1861年のアメリカを忠実に再現している。誇張のない演出は、誠実というか、真摯というか、丹念に丹念に作られており、ハリウッド的なエンターテインメント性はいささかも感じられない。
それがまた独特の味わいを醸し出している。
北軍に包囲され、窮地に陥ったゲリラは、ローレンスという街を襲撃し、すべての男性を北軍とみなして虐殺する。
これは実話であり、殺された男性は、兵士でも北軍でもなかった。
ジェイクとホルトは、狂った仲間たちを見ながら、殺戮には手を貸さなかった。
戦争という狂気は、人間の善性を麻痺させる。そこでは、まったく無意味で陰惨な殺戮が繰り返される。いかに戦争が愚かなことか、映画は痛切に訴えてくる。
また、ホルトが慕う主人ジョージが死に、ホルトは悲しみにくれるのだが、ホルトは初めて「自由」を感じる。南北戦争の争点であった奴隷制度が、どれほど黒人の心を縛り、苦しめていたのか。さまざまなシーンで描かれている。
こんな正統派な映画は見たことがない。
なんのてらいもなく、男の友情や人を許すこと、家族愛が描かれる。それなのにクサくない。それほどに完成度が高いのだ。
2006年09月06日
バーティカル・リミット
まず、広大なスケールとアクションのすごさに度肝を抜かれ、強烈なビジュアルが目に焼き付く。
最高峰ヒマラヤ山脈は、人を寄せ付けない威厳を放ち、すさまじいほどに美しい。
この危険な山を征服しようと人々は挑み続ける。限界に挑戦し、誰もが果たせなかった夢、登頂を実現しようとする。
八方を急斜面で囲まれ、天候の変化を予測できず登山家たちからもっとも恐れられている山K2。
ここに挑み、悲劇に見舞われる若い登山家の兄妹がいた。
兄は、妹とその登頂チームを助けるために、想像を絶する救出作戦を決行することになる。
登頂だけでも危険だが、さらにそこには制約があった。
人間の肉体の限界、命を持ちこたえられる時間はわずか22時間。果たして救い出すことができるのか――。
ロケは、ニュージーランドの南アルプス山脈にあるクック山脈で6カ月にわたって行われたらしい。K2に景観が似ていたからだ。
標高8000メートルでのロケ。本物の雪崩と爆破を起こした。
危険の中での撮影のため、クルーとキャストに与える危険を最小限に抑える登山装備係や、山の天候を監視して評価する山の安全確認係、タレント安全確認係など万全の安全体制を敷いたという。
真実味を増すために世界的に著名な登山家も参加。
その中の一人、エド・ベスターズは本人の役で作品中に登場している。
俳優たちは1カ月間、登山家たちと共にトレーニングを積んだ。
兄を「バットマン&ロビン」のクリス・オドネル、妹を「エンド・オブ・デイズ」のロビン・タニーが演じ、監督は「マスク・オブ・ゾロ」のヒットメーカー、マーティン・キャンベル。
キャンベルファンの期待に違わない出来映えだと思う。
最高峰ヒマラヤ山脈は、人を寄せ付けない威厳を放ち、すさまじいほどに美しい。
この危険な山を征服しようと人々は挑み続ける。限界に挑戦し、誰もが果たせなかった夢、登頂を実現しようとする。
八方を急斜面で囲まれ、天候の変化を予測できず登山家たちからもっとも恐れられている山K2。
ここに挑み、悲劇に見舞われる若い登山家の兄妹がいた。
兄は、妹とその登頂チームを助けるために、想像を絶する救出作戦を決行することになる。
登頂だけでも危険だが、さらにそこには制約があった。
人間の肉体の限界、命を持ちこたえられる時間はわずか22時間。果たして救い出すことができるのか――。
ロケは、ニュージーランドの南アルプス山脈にあるクック山脈で6カ月にわたって行われたらしい。K2に景観が似ていたからだ。
標高8000メートルでのロケ。本物の雪崩と爆破を起こした。
危険の中での撮影のため、クルーとキャストに与える危険を最小限に抑える登山装備係や、山の天候を監視して評価する山の安全確認係、タレント安全確認係など万全の安全体制を敷いたという。
真実味を増すために世界的に著名な登山家も参加。
その中の一人、エド・ベスターズは本人の役で作品中に登場している。
俳優たちは1カ月間、登山家たちと共にトレーニングを積んだ。
兄を「バットマン&ロビン」のクリス・オドネル、妹を「エンド・オブ・デイズ」のロビン・タニーが演じ、監督は「マスク・オブ・ゾロ」のヒットメーカー、マーティン・キャンベル。
キャンベルファンの期待に違わない出来映えだと思う。
2006年09月04日
オール・アバウト・マイ・マザー
スペインの映画監督ペドロ・アルモドバルが、母とのきずなを描いた、ある意味メロドラマ。
ただし最初に断っておかなければならないのは、登場人物達が、アルモドバルの映画を見たことのある人ならおなじみの“変な人”たちばかりなのだ。
街頭で男性を誘惑する女装の男性が複数登場するし、よりによってそうした男性に恋し、妊娠する修道女がいる。
または麻薬中毒の女性を愛する同性愛者の女優もいる……。
こうした“変な人”たちが織りなす感動的で、上質なメロドラマ。
物語は雨中の悲劇的な交通事故から急展開をとげていく。
マヌエラはマドリードで臓器移植コーディネーターをしながら、息子エステバンを独りで育て上げてきた。
息子はしきりに父親がだれか知りたがるが、母はなぜか返事を拒む。
そして息子が17歳の誕生日を迎え、ついに父親がだれかを打ち明けようとしていたその夜に事故は起こるのだ。
マヌエラはずっと会わずにきた伴侶を探し当て、息子の死を知らせるため、かつてエステバンを身ごもった思い出の街バルセロナへと向かう。
アルモドバルの映画では、いつもメロドラマ流れに乗りながら、前述の“変な人たち”、いわば、自分の欲望にまめである分、さまざまな困難やアイデンティティーの分裂に悩まされる人たちを好んで描いてきた。
そのため、しばしばドラマ的な均衡が犠牲になってきた面も否めない。もちろんそれが彼の映画の魅力でもあるのだが……。
だけど、この作品ではアルモドバル的な過剰さがドラマとしての均衡を崩すことなく微妙なバランスを保ち続ける。
というか、両者が互いに互いを煽りあい、相乗効果を生みだす。
妙に芸術めかした難解な映画にも、大がかりなジェットコースター的スペクタクルにも向かわず、ひたすらメロドラマの洗練を目指す彼のような映画作家こそ、現在の映画界で貴重な存在といえるかもしれない。
ただし最初に断っておかなければならないのは、登場人物達が、アルモドバルの映画を見たことのある人ならおなじみの“変な人”たちばかりなのだ。
街頭で男性を誘惑する女装の男性が複数登場するし、よりによってそうした男性に恋し、妊娠する修道女がいる。
または麻薬中毒の女性を愛する同性愛者の女優もいる……。
こうした“変な人”たちが織りなす感動的で、上質なメロドラマ。
物語は雨中の悲劇的な交通事故から急展開をとげていく。
マヌエラはマドリードで臓器移植コーディネーターをしながら、息子エステバンを独りで育て上げてきた。
息子はしきりに父親がだれか知りたがるが、母はなぜか返事を拒む。
そして息子が17歳の誕生日を迎え、ついに父親がだれかを打ち明けようとしていたその夜に事故は起こるのだ。
マヌエラはずっと会わずにきた伴侶を探し当て、息子の死を知らせるため、かつてエステバンを身ごもった思い出の街バルセロナへと向かう。
アルモドバルの映画では、いつもメロドラマ流れに乗りながら、前述の“変な人たち”、いわば、自分の欲望にまめである分、さまざまな困難やアイデンティティーの分裂に悩まされる人たちを好んで描いてきた。
そのため、しばしばドラマ的な均衡が犠牲になってきた面も否めない。もちろんそれが彼の映画の魅力でもあるのだが……。
だけど、この作品ではアルモドバル的な過剰さがドラマとしての均衡を崩すことなく微妙なバランスを保ち続ける。
というか、両者が互いに互いを煽りあい、相乗効果を生みだす。
妙に芸術めかした難解な映画にも、大がかりなジェットコースター的スペクタクルにも向かわず、ひたすらメロドラマの洗練を目指す彼のような映画作家こそ、現在の映画界で貴重な存在といえるかもしれない。
- カテゴリー
- 検索
- 最近のコメント
-
- 十五才 学校IV
- └ click the next website 11/28
- └ roxy 11/30
- └ kubah mesjid enamel 01/29
- └ kedged.rcbrevisions.com/disarm/centum.html 04/12
- └ kоnyĞ° еscоrt 12/11
- └ スーパーコピー 税関 没収 類語 02/29
- └ ktokkisa 01/18
- └ Frankflism 01/24
- └ Thomastrept 01/26
- 十五才 学校IV
- 最近のトラックバック
-
-
スナッチ
- molbiol.ru
- »molbiol.ru
- 05/24 12:43
- what is foods
- »www.myvipon.com
- 05/24 11:47
- please click the next internet page
- »heylink.me
- 05/24 11:35
- Cheapest dedicated server
- »Cheapest dedicated server
- 02/04 22:25
- actors with the best voices
- »actors with the best voices
- 10/14 03:24
- férias sem fim
- »férias sem fim
- 03/23 09:23
- 3 bhk
- »3 bhk
- 01/10 16:58
- toda la información necesaria sobre rinoplastia
- »toda la información necesaria sobre rinoplastia
- 11/18 21:35
- Occupational Psychology
- »Occupational Psychology
- 11/05 02:01
-
スナッチ
- ブログ・アクセサリー
-
-

track feed -
-
-