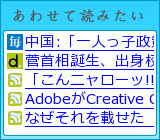自宅でDVD三昧!~映画・ドラマどんと来い!
もちろん映画館で見る大画面の映画の雰囲気は最高。でも自宅でまったりDVD三昧というのも良い物だ。人目を気にせず見た映画DVD・ドラマDVDの感想など書き散らしてみたり。
2006年07月31日
ミリオンズ
幼い2人の兄弟が歓声をあげながら、野原を自転車で走ってゆく。青空の下、野に一面に咲く黄色い花が、黄色い帯となって飛んでゆく映像の美しさ。子どもっていいな、子ども時代って楽しかったなと思わせる。
兄弟は少し前にお母さんを亡くし、お父さんと3人で、イギリスのある街に暮らしている。ある日、兄弟が線路わきに作った段ボールの秘密基地に、ポンド札がいっぱいに詰まったボストン・バッグが降ってきた。中身の総額は22万9320ポンド(約4600万円)!
ポンドがユーロにかわる12日前という設定。こんなこともあるかもしれない。ある犯罪組織が、焼却炉行きのポンド紙幣を積んだ列車から金を盗み出しては外に投げていたのだ。降ってきたのは、あとから回収するはずのバッグの1つだった。
そうとは知らず神様の贈り物だと思い込み、貧しい人々を助けようと考える弟。お兄ちゃんの方は現実的で、ゲームや自転車を買ったあと、これを元手にひともうけを目論む。
紙幣がただの紙切れになる前に使ってしまおうと兄弟は奮闘するが、子どもには案外難しかった。募金をしようにも多額な募金は怪しまれる。銀行は口座を開かせてくれないし、投資用に家を買おうにも不動産屋は相手にしてくれない。そんな中、お金を見つけたお父さんは……。
刻一刻とポンドがユーロに変わる日は近づいてくる。お金を追って、組織の手も伸びる。さて兄弟は、無事にお金を使いきれるのか?
架空の設定も活き、子供の純真さ、悪賢さ、大人の狡さがほどよくブレンドされた楽しい映画。そして小さな兄弟が、お金が必ずしも人をしあわせにするわけではないことを学ぶとき、観る者は身につまされるだろう。
12日間で大きく成長した2人に最後、奇跡が起きる。神様の贈り物?
子どもはお金で到底買えないものでも手に入れる想像力を持っている。これこそが神様の贈り物に違いない。
兄弟は少し前にお母さんを亡くし、お父さんと3人で、イギリスのある街に暮らしている。ある日、兄弟が線路わきに作った段ボールの秘密基地に、ポンド札がいっぱいに詰まったボストン・バッグが降ってきた。中身の総額は22万9320ポンド(約4600万円)!
ポンドがユーロにかわる12日前という設定。こんなこともあるかもしれない。ある犯罪組織が、焼却炉行きのポンド紙幣を積んだ列車から金を盗み出しては外に投げていたのだ。降ってきたのは、あとから回収するはずのバッグの1つだった。
そうとは知らず神様の贈り物だと思い込み、貧しい人々を助けようと考える弟。お兄ちゃんの方は現実的で、ゲームや自転車を買ったあと、これを元手にひともうけを目論む。
紙幣がただの紙切れになる前に使ってしまおうと兄弟は奮闘するが、子どもには案外難しかった。募金をしようにも多額な募金は怪しまれる。銀行は口座を開かせてくれないし、投資用に家を買おうにも不動産屋は相手にしてくれない。そんな中、お金を見つけたお父さんは……。
刻一刻とポンドがユーロに変わる日は近づいてくる。お金を追って、組織の手も伸びる。さて兄弟は、無事にお金を使いきれるのか?
架空の設定も活き、子供の純真さ、悪賢さ、大人の狡さがほどよくブレンドされた楽しい映画。そして小さな兄弟が、お金が必ずしも人をしあわせにするわけではないことを学ぶとき、観る者は身につまされるだろう。
12日間で大きく成長した2人に最後、奇跡が起きる。神様の贈り物?
子どもはお金で到底買えないものでも手に入れる想像力を持っている。これこそが神様の贈り物に違いない。
2006年07月30日
ダブル・ジョパディー
「ダブル・ジョパディー」とは、二重処罰の禁止の意。だれもが同一の犯罪で二度有罪にはならないということである。アメリカ合衆国憲法修正第5条で規定されている。この法律をテーマに母親の我が子への深い愛情と、夫に対する復讐劇をスリリングなタッチでまとめ上げている。
シアトル郊外に住む主婦リビー。彼女は、実業家の夫ニック、最愛の息子マティと幸せな日々を過ごしていた。
ある日突然、夫殺害の罪を着せられ、刑務所で服役生活を余儀なくされる。親友に預けた息子のことが心から離れないリビー。行方知れずになった2人を探し当てた彼女は、衝撃の事実を知る。死んだはずの夫が生きていた……。
戸惑いと混乱のふちに突き落とされた彼女に、ある女囚が「ダブル・ジョパディー」という言葉をささやく。そのひとことがリビーを奮い立たせた。夫への復讐と息子との再会を果たすために、一日も早い出所を待つリビー。
そして6年の月日が経過し、仮釈放の日を迎えた彼女は保護監察官トラヴィスの監視下に。ついに彼女の逃亡と追跡の日々が始まる……。 リビー役を演じるのは、アシュレイ・ジャッド。傷つきやすいもろさと強さを備えた母親役を体当たりで見事に演じている。トミー・リー・ジョーンズが保護監察官役に。いつもながらの重厚な演技で、作品全体を引き締めている。
監督は、オペラの演出も手がけるブルース・ベレスフォード。
日本の法体系においては、あまり馴染のない二重処罰の禁止という制度。その法律の盲点をつくかのようなドラマの筋立てが巧みである。
始めから終わりまでスリルあふれるシーンの連続で、アシュレイ・ジャッドの熱演も特筆すべきだろう。対照的に我が子に対する深い母の愛情が、物語全体を温かく包み込む。
ラストシーンの心安らぐ瞬間は、現代における一種のカタルシス劇としての効用をそなえているといっていい。
母は強く、偉大である。
シアトル郊外に住む主婦リビー。彼女は、実業家の夫ニック、最愛の息子マティと幸せな日々を過ごしていた。
ある日突然、夫殺害の罪を着せられ、刑務所で服役生活を余儀なくされる。親友に預けた息子のことが心から離れないリビー。行方知れずになった2人を探し当てた彼女は、衝撃の事実を知る。死んだはずの夫が生きていた……。
戸惑いと混乱のふちに突き落とされた彼女に、ある女囚が「ダブル・ジョパディー」という言葉をささやく。そのひとことがリビーを奮い立たせた。夫への復讐と息子との再会を果たすために、一日も早い出所を待つリビー。
そして6年の月日が経過し、仮釈放の日を迎えた彼女は保護監察官トラヴィスの監視下に。ついに彼女の逃亡と追跡の日々が始まる……。 リビー役を演じるのは、アシュレイ・ジャッド。傷つきやすいもろさと強さを備えた母親役を体当たりで見事に演じている。トミー・リー・ジョーンズが保護監察官役に。いつもながらの重厚な演技で、作品全体を引き締めている。
監督は、オペラの演出も手がけるブルース・ベレスフォード。
日本の法体系においては、あまり馴染のない二重処罰の禁止という制度。その法律の盲点をつくかのようなドラマの筋立てが巧みである。
始めから終わりまでスリルあふれるシーンの連続で、アシュレイ・ジャッドの熱演も特筆すべきだろう。対照的に我が子に対する深い母の愛情が、物語全体を温かく包み込む。
ラストシーンの心安らぐ瞬間は、現代における一種のカタルシス劇としての効用をそなえているといっていい。
母は強く、偉大である。
2006年07月29日
アメリカン・ビューティー
アメリカの中流家庭を舞台にして、現代人が抱える閉塞感、倦怠感に押しつぶされる家族の人間模様をコミカルに、そして残酷に描き出している。
郊外の新興住宅地に住むレスター・バーナムは、雑誌社で広告の仕事をする中年サラリーマン。住宅ローンを抱えながらリストラの風にさらされる。一方の妻キャロリンは、そんな夫にうんざりしながらも不動産のブローカーとして敏腕を振るい、家ではおしゃれな生活にのめり込んでいく。そして一人娘のジェーンは、怒りと不安に揺れる典型的なティーンエージャーだ。
ある日、レスターはジェーンの友達アンジェラを一目見た途端、メロメロに。娘の軽蔑を一身に受けながらも、アンジェラへの思いは募るばかり。他方、欲求不満のキャロリンは、同業者の“不動産王”に急接近。そして二人は、ついに危険な坂道を転げ落ちることに……。
主人公を演じるのはケビン・スペイシー。初のダメ男役に挑み、もうひとつの顔を見せてくれる。キャロリン役のアネット・ベニングも、いままでのゴージャスなイメージを一変、自ら描く“サクセスストーリー”にとりつかれる見苦しい女を体当たりで演じる。
監督は、イギリス演劇界で活躍する新進気鋭の演出家サム・メンデス。本作で監督デビューを飾った。テレビのコメディー・ライターとして名をはせたアラン・ボールが書き下ろした脚本は、不思議な世界をつむぎ出し、登場人物の内面の葛藤(かっとう)を巧みに表現している。
ゴールデングローブ賞で最優秀作品賞、監督賞、脚本賞に輝いた。
“アメリカン・ビューティー”とは、映画の中で、キャロリンが栽培している米国産の赤いバラの名前。美しいバラは、見る者を魅了する。しかし、そこには鋭いトゲが潜んでいる――。
豊かで享楽的な社会を土壌に咲いた甘美な“バラ”。その魅惑的な刺激のとりこになり、運命の歯車を狂わせていく、悲しくもこっけいな人生……。しかし、途中までのコミカルな色を交えた展開から一転、ラストシーンの衝撃的な結末によるコントラストは、現代にあって自覚しがたい人間の“喜劇的な悲劇性”を見事に浮かび上がらせている。
郊外の新興住宅地に住むレスター・バーナムは、雑誌社で広告の仕事をする中年サラリーマン。住宅ローンを抱えながらリストラの風にさらされる。一方の妻キャロリンは、そんな夫にうんざりしながらも不動産のブローカーとして敏腕を振るい、家ではおしゃれな生活にのめり込んでいく。そして一人娘のジェーンは、怒りと不安に揺れる典型的なティーンエージャーだ。
ある日、レスターはジェーンの友達アンジェラを一目見た途端、メロメロに。娘の軽蔑を一身に受けながらも、アンジェラへの思いは募るばかり。他方、欲求不満のキャロリンは、同業者の“不動産王”に急接近。そして二人は、ついに危険な坂道を転げ落ちることに……。
主人公を演じるのはケビン・スペイシー。初のダメ男役に挑み、もうひとつの顔を見せてくれる。キャロリン役のアネット・ベニングも、いままでのゴージャスなイメージを一変、自ら描く“サクセスストーリー”にとりつかれる見苦しい女を体当たりで演じる。
監督は、イギリス演劇界で活躍する新進気鋭の演出家サム・メンデス。本作で監督デビューを飾った。テレビのコメディー・ライターとして名をはせたアラン・ボールが書き下ろした脚本は、不思議な世界をつむぎ出し、登場人物の内面の葛藤(かっとう)を巧みに表現している。
ゴールデングローブ賞で最優秀作品賞、監督賞、脚本賞に輝いた。
“アメリカン・ビューティー”とは、映画の中で、キャロリンが栽培している米国産の赤いバラの名前。美しいバラは、見る者を魅了する。しかし、そこには鋭いトゲが潜んでいる――。
豊かで享楽的な社会を土壌に咲いた甘美な“バラ”。その魅惑的な刺激のとりこになり、運命の歯車を狂わせていく、悲しくもこっけいな人生……。しかし、途中までのコミカルな色を交えた展開から一転、ラストシーンの衝撃的な結末によるコントラストは、現代にあって自覚しがたい人間の“喜劇的な悲劇性”を見事に浮かび上がらせている。
2006年07月28日
チャーリーとチョコレート工場
子供たちに大人気のウォンカのチョコレートは魔法のチョコ。工場の門は閉鎖され、働く者もいないのに、工場からは毎日、おいしいチョコレートが世界中に出荷されてゆくのだから。
そんな謎の工場が、このたび5人の子供を招待するという。招待されるのは、ウォンカの板チョコに入っているゴールデン・チケットを引き当てた幸運者。世界中の子供たちがチケットを当てようと狂奔したのだ。
さて招待日当日、伝説の工場主ウォンカ氏(ジョニー・デップ)に案内され、チャーリーをはじめ当選者たちが見たものは、お菓子の森、ナッツを割るリス、チョコレートの川、働きながら歌う小人たち……。
原作は、ロアルド・ダールの「チョコレート工場の秘密」。世界中で愛され、昨年、出版40周年を迎えたこのファンタジー小説の映画化には、ティム・バートン監督の奔放なる想像力を待たなければならなかった。スクリーンからは、「楽しさ」があふれだす。
それにしても、こんな工場を作ってしまうウォンカ氏は、いったい何者なのか? “秘密”は実は、ここにある。浮世ばなれしたウォンカ氏も人の子だったのだ――。
親の生き方は、なかなか理解できないものである。親に反旗を翻した結果が現在の自分の姿だったりしないだろうか。でもそんな自分の生き方が、今度は許せなかったりもする。
どんな親でも愛したいものである。親との和解は人生の大いなるテーマだろう。ファンタジーの世界に遊ぶうち、いつしか映画は観る者の痛いところを突いてくる。
そういえばチョコレートは甘いばかりではなく、ビター・チョコというのもあったっけ。そしてビターの味が、ビターの先に広がる甘さがわかるのが大人なのであった。
大人だって大好きなチョコレート。この映画も、子供だけのものではない。
そんな謎の工場が、このたび5人の子供を招待するという。招待されるのは、ウォンカの板チョコに入っているゴールデン・チケットを引き当てた幸運者。世界中の子供たちがチケットを当てようと狂奔したのだ。
さて招待日当日、伝説の工場主ウォンカ氏(ジョニー・デップ)に案内され、チャーリーをはじめ当選者たちが見たものは、お菓子の森、ナッツを割るリス、チョコレートの川、働きながら歌う小人たち……。
原作は、ロアルド・ダールの「チョコレート工場の秘密」。世界中で愛され、昨年、出版40周年を迎えたこのファンタジー小説の映画化には、ティム・バートン監督の奔放なる想像力を待たなければならなかった。スクリーンからは、「楽しさ」があふれだす。
それにしても、こんな工場を作ってしまうウォンカ氏は、いったい何者なのか? “秘密”は実は、ここにある。浮世ばなれしたウォンカ氏も人の子だったのだ――。
親の生き方は、なかなか理解できないものである。親に反旗を翻した結果が現在の自分の姿だったりしないだろうか。でもそんな自分の生き方が、今度は許せなかったりもする。
どんな親でも愛したいものである。親との和解は人生の大いなるテーマだろう。ファンタジーの世界に遊ぶうち、いつしか映画は観る者の痛いところを突いてくる。
そういえばチョコレートは甘いばかりではなく、ビター・チョコというのもあったっけ。そしてビターの味が、ビターの先に広がる甘さがわかるのが大人なのであった。
大人だって大好きなチョコレート。この映画も、子供だけのものではない。
ザ・ホワイトハウス<ファースト・シーズン>
以前から手元に置いておきたかった「ザ・ホワイトハウス(原題:The West Wing)」を遂に購入。
NHKの海外ドラマの中でも、この作品が一番気に入っている。
一見固く難解に思える政治ドラマながら、丁寧な脚本による心の動きが描写され、大統領はもちろん、ホワイトハウス上級職員たちが実に人間くさく、そして魅力的だ。
既に<サード・シーズン>までが発売されているが、初心に戻って、<ファースト・シーズン>からその人間ドラマに浸っていこうと思っている。
NHKの海外ドラマの中でも、この作品が一番気に入っている。
一見固く難解に思える政治ドラマながら、丁寧な脚本による心の動きが描写され、大統領はもちろん、ホワイトハウス上級職員たちが実に人間くさく、そして魅力的だ。
既に<サード・シーズン>までが発売されているが、初心に戻って、<ファースト・シーズン>からその人間ドラマに浸っていこうと思っている。
2006年07月27日
博士の愛した数式
交通事故の後遺症で、天才数学者の博士(寺尾聰)は、記憶がたった80分しかもたない。何を話していいか混乱した時、言葉の代わりに数字を持ち出す。
相手を敬う心を忘れず、常に数学のそばから離れようとしない。そんな、いささか風変わりな博士のもとで働くことになったシングルマザーの家政婦・杏子(深津絵里)。その10歳の息子(齋藤隆成)を、博士は、“ルート(√)”と呼ぶ。博士と語り合ううち、二人は数式の中に秘められた、美しい意味を知る――。
芥川賞作家・小川洋子のベストセラーとなった同名小説を、『雨あがる』の小泉堯史監督が映画化した。
この映画には、数学への憧憬や、数字の美しさへの心酔がちりばめられている。
ごく普通の人からみれば、数学者の振る舞いや、数字に意味を見いだそうとする行為は、奇異に思えるものだ。あまりにも純粋に率直に示される、博士の数学への深い愛情が、家政婦とその息子にも、だんだんとうつっていく様子がみてとれる。80分ごとに記憶をなくす博士は、常に相手を初対面として接する。けれど、そこには人としての佇まいの美しさがある。
原作の面白さ、魅力をあまねく引き出しながら、また違った、映画ならではの世界を構築している。主だった登場人物は、たった5人。長じて、数学教師となった“ルート”を演じる吉岡秀隆と、浅丘ルリ子を加えた5人の役者たちは、どの一人が欠けても、均衡が崩れるかのような、絶妙な緊張感で存在する。
数学になぞらえていうならば、それぞれが素数の美しさ(!)を保ちながら、互いに慕わしさをかもしだしている。
相手を敬う心を忘れず、常に数学のそばから離れようとしない。そんな、いささか風変わりな博士のもとで働くことになったシングルマザーの家政婦・杏子(深津絵里)。その10歳の息子(齋藤隆成)を、博士は、“ルート(√)”と呼ぶ。博士と語り合ううち、二人は数式の中に秘められた、美しい意味を知る――。
芥川賞作家・小川洋子のベストセラーとなった同名小説を、『雨あがる』の小泉堯史監督が映画化した。
この映画には、数学への憧憬や、数字の美しさへの心酔がちりばめられている。
ごく普通の人からみれば、数学者の振る舞いや、数字に意味を見いだそうとする行為は、奇異に思えるものだ。あまりにも純粋に率直に示される、博士の数学への深い愛情が、家政婦とその息子にも、だんだんとうつっていく様子がみてとれる。80分ごとに記憶をなくす博士は、常に相手を初対面として接する。けれど、そこには人としての佇まいの美しさがある。
原作の面白さ、魅力をあまねく引き出しながら、また違った、映画ならではの世界を構築している。主だった登場人物は、たった5人。長じて、数学教師となった“ルート”を演じる吉岡秀隆と、浅丘ルリ子を加えた5人の役者たちは、どの一人が欠けても、均衡が崩れるかのような、絶妙な緊張感で存在する。
数学になぞらえていうならば、それぞれが素数の美しさ(!)を保ちながら、互いに慕わしさをかもしだしている。
草ぶきの学校
子どもたちの純粋な瞳は、喜びも悲しみも、真正面から映し出す。
その小さな胸に、大人以上の葛藤の嵐が吹くこともある。
決して楽しさだけじゃなかった、けれども幸せだった子ども時代――。
1962年ごろ、文化革命前の中国農村部に暮らした子どもたちを描いた作品。砂にまみれ、風に吹かれて育まれた、懐かしい日々が思い起こされる。
友情、家族愛など、少年の視線から見た日常が鮮やか。
戦後の日本とも重なるノスタルジィで、地味ながら爽やかに浸らせてくれる。
その小さな胸に、大人以上の葛藤の嵐が吹くこともある。
決して楽しさだけじゃなかった、けれども幸せだった子ども時代――。
1962年ごろ、文化革命前の中国農村部に暮らした子どもたちを描いた作品。砂にまみれ、風に吹かれて育まれた、懐かしい日々が思い起こされる。
友情、家族愛など、少年の視線から見た日常が鮮やか。
戦後の日本とも重なるノスタルジィで、地味ながら爽やかに浸らせてくれる。
2006年07月26日
ジャンヌ・ダルク
ジャンヌ・ダルクといえば、知らない人はいない500年前のフランスの英雄だ。「神のお告げを受けた」と祖国を救うために戦い、勝利に導いた後、魔女として火あぶりにされる。
ミラ・ジョヴォヴィッチ演じるジャンヌ・ダルクは、実にエキセントリックでいちずだ。フランスを守るために、シャルル7世を戴冠させるために、まるで憑かれたように戦い続ける。田舎娘で戦った経験などまるでないのに鎧に身を包み旗を振り上げ「フォロー・ミー!」(私についてきて)と叫ぶ。戦いの先頭に立って、荒くれ兵士たちの士気を高め勇気を鼓舞する。「ここに神の意志がある。だから決して負けはしないのだ」と。
ここでのジャンヌは聖処女というよりも、人間くさい。神の言葉を信じ突き進むのだが、多くの血が流れる戦場を見て動揺し、裏切りに怒り、神の愛を疑う。
だれもが最初は小娘だと馬鹿にして自分についてこないことに腹を立てたりする。また、火あぶりを恐れ、神に助けを乞う。
私たちとはかけ離れた歴史上の人物だったのが、一気に等身大の人間として、もし自分だったら、もし同じ立場だったら、と考えざるを得ないような目線で描かれていく。血にまみれる戦争の狂気に放り込まれた少女は、さぞ怖かっただろう。
監督は、「グラン・ブルー」や「ニキータ」でフランス映画界の地位を不動のものとし、「レオン」「フィフス・エレメント」でハリウッドに打って出たリュック・ベッソンだ。彼は、ジャンヌ・ダルクという人物を徹底的に研究しベッソン流の解釈で、独特の映像世界を作り上げた。神の啓示の描写は圧巻だ。
歴史は語る。勝つためには勝利への信念がなくてはならず、さらに気をつけるべきものは嫉妬とねたみであるということを。
ミラ・ジョヴォヴィッチ演じるジャンヌ・ダルクは、実にエキセントリックでいちずだ。フランスを守るために、シャルル7世を戴冠させるために、まるで憑かれたように戦い続ける。田舎娘で戦った経験などまるでないのに鎧に身を包み旗を振り上げ「フォロー・ミー!」(私についてきて)と叫ぶ。戦いの先頭に立って、荒くれ兵士たちの士気を高め勇気を鼓舞する。「ここに神の意志がある。だから決して負けはしないのだ」と。
ここでのジャンヌは聖処女というよりも、人間くさい。神の言葉を信じ突き進むのだが、多くの血が流れる戦場を見て動揺し、裏切りに怒り、神の愛を疑う。
だれもが最初は小娘だと馬鹿にして自分についてこないことに腹を立てたりする。また、火あぶりを恐れ、神に助けを乞う。
私たちとはかけ離れた歴史上の人物だったのが、一気に等身大の人間として、もし自分だったら、もし同じ立場だったら、と考えざるを得ないような目線で描かれていく。血にまみれる戦争の狂気に放り込まれた少女は、さぞ怖かっただろう。
監督は、「グラン・ブルー」や「ニキータ」でフランス映画界の地位を不動のものとし、「レオン」「フィフス・エレメント」でハリウッドに打って出たリュック・ベッソンだ。彼は、ジャンヌ・ダルクという人物を徹底的に研究しベッソン流の解釈で、独特の映像世界を作り上げた。神の啓示の描写は圧巻だ。
歴史は語る。勝つためには勝利への信念がなくてはならず、さらに気をつけるべきものは嫉妬とねたみであるということを。
- 最近のエントリー
-
[
 新着情報]
新着情報]
- カテゴリー
- 検索
- 最近のコメント
-
- 十五才 学校IV
- └ click the next website 11/28
- └ roxy 11/30
- └ kubah mesjid enamel 01/29
- └ kedged.rcbrevisions.com/disarm/centum.html 04/12
- └ kоnyĞ° еscоrt 12/11
- └ スーパーコピー 税関 没収 類語 02/29
- └ ktokkisa 01/18
- └ Frankflism 01/24
- └ Thomastrept 01/26
- 十五才 学校IV
- 最近のトラックバック
-
-
スナッチ
- may loc nuoc dien giai ion kiem
- »www.aros.bigbadrobots.com
- 05/23 04:07
- school erp
- »www.mythrite.com
- 05/23 02:26
- ProVitra Review
- »alase.net
- 05/23 01:19
- Cheapest dedicated server
- »Cheapest dedicated server
- 02/04 22:25
- actors with the best voices
- »actors with the best voices
- 10/14 03:24
- férias sem fim
- »férias sem fim
- 03/23 09:23
- 3 bhk
- »3 bhk
- 01/10 16:58
- toda la información necesaria sobre rinoplastia
- »toda la información necesaria sobre rinoplastia
- 11/18 21:35
- Occupational Psychology
- »Occupational Psychology
- 11/05 02:01
-
スナッチ
- ブログ・アクセサリー
-
-

track feed -
-
-