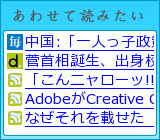自宅でDVD三昧!~映画・ドラマどんと来い!
もちろん映画館で見る大画面の映画の雰囲気は最高。でも自宅でまったりDVD三昧というのも良い物だ。人目を気にせず見た映画DVD・ドラマDVDの感想など書き散らしてみたり。
« 2006年07月 | メイン | 2006年09月 »
2006年08月29日
ホワット・ライズ・ビニース
娯楽映画の王道としてサスペンス映画があり、その頂点にはヒッチコックがいる。
ロバート・ゼメキス監督が、ヒッチコックを越えるスリラーを目指した本作。
「ヒッチコックが生きていてCGを使えたらどうするか」――ゼメキス監督は、CGの担当者にこう指示したという。
「タイタニック」のCGを制作した担当者は「コンピューター技術は映画の物語を深めるためにある」という考え方から、どこでCGが使われたのかを感じさせない自然な映像をつくりあげた。
著名な数学者のノーマン(ハリソン・フォード)と、妻のクレア(ミシェル・ファイファー)は、ヴァーモントの湖のほとりの大きな家に住んでいた。クレアは娘を溺愛していたが、娘が大学に入って家を出てしまう。寂しさに苛まれるクレアの周りで、不気味な現象が起こり始める。
BGMが消え、緊張感が高まっていくと、突然、わっと驚かせるような画面が飛び出す。それが5分に1回はやってくる。
目の肥えた人だと、そろそろ来るぞと冷めた目で見てしまいがちだが、この映画ならハマるだろう。それは、物語が静かに静かに進行するからだ。見るものを構えさせない、平凡な生活が淡々と描かれている。
これは、ハリソン・フォードとミシェル・ファイファーの演技力によるところが大きい。
特に前半のハリソン・フォードは、いるのかいないのかわからないほど存在を感じさせない。個性を感じさせない演技から、演じるということの一側面を考えさせられる。
この映画のテーマは、男の浮気。
夫のたった一度の過ちから、家庭が崩壊し、夫は身を滅ぼすことになる。
サスペンス映画で、このテーマが扱われることは多い。
2時間、ハラハラドキドキを楽しむスリラー映画。男女を問わず恐怖感を与え続けられるが、特に世の男性諸君は浮気の恐ろしさを感じることだろう。
だが、これは説教くさい映画ではない。見終わったあと、やっぱり浮気は恐いな、そんな気持ちが残るのだ。
アメリカの離婚率は、約50%と高い。現代のハリウッド映画のほとんどのテーマは家庭の崩壊と再生である。
家庭の崩壊から起こる悪影響は数知れない――犠牲になる子ども、少年犯罪、精神の病、麻薬、性犯罪などなど。
金と時間が余ると、人はろくなことをしない。
金はないくらいの方が幸せではないか。
また、家庭という幸福の基盤の大切さ。映画を見ながら、そんなことを思った。
ロバート・ゼメキス監督が、ヒッチコックを越えるスリラーを目指した本作。
「ヒッチコックが生きていてCGを使えたらどうするか」――ゼメキス監督は、CGの担当者にこう指示したという。
「タイタニック」のCGを制作した担当者は「コンピューター技術は映画の物語を深めるためにある」という考え方から、どこでCGが使われたのかを感じさせない自然な映像をつくりあげた。
著名な数学者のノーマン(ハリソン・フォード)と、妻のクレア(ミシェル・ファイファー)は、ヴァーモントの湖のほとりの大きな家に住んでいた。クレアは娘を溺愛していたが、娘が大学に入って家を出てしまう。寂しさに苛まれるクレアの周りで、不気味な現象が起こり始める。
BGMが消え、緊張感が高まっていくと、突然、わっと驚かせるような画面が飛び出す。それが5分に1回はやってくる。
目の肥えた人だと、そろそろ来るぞと冷めた目で見てしまいがちだが、この映画ならハマるだろう。それは、物語が静かに静かに進行するからだ。見るものを構えさせない、平凡な生活が淡々と描かれている。
これは、ハリソン・フォードとミシェル・ファイファーの演技力によるところが大きい。
特に前半のハリソン・フォードは、いるのかいないのかわからないほど存在を感じさせない。個性を感じさせない演技から、演じるということの一側面を考えさせられる。
この映画のテーマは、男の浮気。
夫のたった一度の過ちから、家庭が崩壊し、夫は身を滅ぼすことになる。
サスペンス映画で、このテーマが扱われることは多い。
2時間、ハラハラドキドキを楽しむスリラー映画。男女を問わず恐怖感を与え続けられるが、特に世の男性諸君は浮気の恐ろしさを感じることだろう。
だが、これは説教くさい映画ではない。見終わったあと、やっぱり浮気は恐いな、そんな気持ちが残るのだ。
アメリカの離婚率は、約50%と高い。現代のハリウッド映画のほとんどのテーマは家庭の崩壊と再生である。
家庭の崩壊から起こる悪影響は数知れない――犠牲になる子ども、少年犯罪、精神の病、麻薬、性犯罪などなど。
金と時間が余ると、人はろくなことをしない。
金はないくらいの方が幸せではないか。
また、家庭という幸福の基盤の大切さ。映画を見ながら、そんなことを思った。
2006年08月25日
グリーン・デスティニー
アメリカや台湾を舞台にして女性を繊細に描いた作品の多かったアン・リー監督による武侠映画。
19世紀初頭、剣の英雄が群雄割拠する時代。許されない愛に苦しむ2組の男女がいた。400年前に作られた秘剣グリーン・デスティニー(碧名剣)の使い手として名を轟かせる英雄リー・ムーバイ(チョウ・ユンファ)と、その女弟子シューリン(ミシェル・ヨー)。もう1組、貴族の娘イェンと盗賊の頭ローもまた身分違いながらも惹かれ、激しく愛しあっていた。
彼らは英雄の剣をめぐる復讐のドラマの中で真実の愛を知っていく。
最も重要な役イェンを演じたチャン・ツィイー。そしてチャン・チェンがローを演じている。
ユンファとチェンも今までで最高のクールさだが、ヨーとツィイーの女性陣の気品も戦いぶりも男性以上にすばらしい。
とくに、二重、三重の引き裂かれの中で、自らの激情と戦いながらも死をもいとわない貴族の娘を演じたツィイーは、こんなに魅力的で最強の女性の存在は、めったに描けるものではないと思う。
「マトリックス」(’99)の世界的大ヒットで注目された香港きっての武術アクション監督ユエン・ウーピンだが、本作は彼にとっての原点ともいえるワイヤーワークとアクロバティックな技闘のコラボレーションの集大成といえる仕上がり。
ハリウッド的な誇張がない分、役者自身のしなやかな身体の躍動があり、かえって洗練されていさえする。
デジタル特殊効果をとり入れつつも、古典的なワイヤーワーク・アクションを駆使したこの作品の方が優れた映画的言語をもったものになっている。
例えば竹やぶでの戦闘シーンの美しさは息を呑むほどだ。
紫禁城全景や広大な砂漠の風景を飛ぶ主人公たち。背景全体を使った飛行シーンをワンシーンワンカットで捉えていく。
そののびやかな空間の移動、スクリーンを駆けめぐる主人公たちの動きは映画の快楽そのものだ。
19世紀初頭、剣の英雄が群雄割拠する時代。許されない愛に苦しむ2組の男女がいた。400年前に作られた秘剣グリーン・デスティニー(碧名剣)の使い手として名を轟かせる英雄リー・ムーバイ(チョウ・ユンファ)と、その女弟子シューリン(ミシェル・ヨー)。もう1組、貴族の娘イェンと盗賊の頭ローもまた身分違いながらも惹かれ、激しく愛しあっていた。
彼らは英雄の剣をめぐる復讐のドラマの中で真実の愛を知っていく。
最も重要な役イェンを演じたチャン・ツィイー。そしてチャン・チェンがローを演じている。
ユンファとチェンも今までで最高のクールさだが、ヨーとツィイーの女性陣の気品も戦いぶりも男性以上にすばらしい。
とくに、二重、三重の引き裂かれの中で、自らの激情と戦いながらも死をもいとわない貴族の娘を演じたツィイーは、こんなに魅力的で最強の女性の存在は、めったに描けるものではないと思う。
「マトリックス」(’99)の世界的大ヒットで注目された香港きっての武術アクション監督ユエン・ウーピンだが、本作は彼にとっての原点ともいえるワイヤーワークとアクロバティックな技闘のコラボレーションの集大成といえる仕上がり。
ハリウッド的な誇張がない分、役者自身のしなやかな身体の躍動があり、かえって洗練されていさえする。
デジタル特殊効果をとり入れつつも、古典的なワイヤーワーク・アクションを駆使したこの作品の方が優れた映画的言語をもったものになっている。
例えば竹やぶでの戦闘シーンの美しさは息を呑むほどだ。
紫禁城全景や広大な砂漠の風景を飛ぶ主人公たち。背景全体を使った飛行シーンをワンシーンワンカットで捉えていく。
そののびやかな空間の移動、スクリーンを駆けめぐる主人公たちの動きは映画の快楽そのものだ。
2006年08月24日
キャラバン
素晴らしく美しく、本物の自然を切り取り、かつ、自然への畏怖に包まれた作品。
村の人から長老とあがめられ、若い頃キャラバンの隊長をつとめてきた人物の息子が死んだ。キャラバン隊長という絶対の権力を譲った息子亡き今、その地位をどうするか。
息子の親友で長老とかつて対立していた男が周囲の信頼を得て隊長になった。しかし、進歩的で合理的な彼の考え方を長老は気に入らない。
まだ幼い孫に期待をかける長老は、無謀にも自分でキャラバンを出すことにする。
2人の対立は何を生むのか。
村はどうなるのか。
撮影は5000メートルを超えるネパール山中で、およそ8カ月をかけて行われた。
ここで見られるのは厳しい自然だけではない。ワンシーンごとの映像が、絵のように完成されている。
黄色い麦畑とヒマラヤ。
キャラバンの牛の群。
ベージュ色の地面に朱色の衣、そして、ターバン。
それもそのはず、長編第1作目というエリック・ヴァリ監督は、元はナショナル・ジオグラフィックの写真家だった。彼はこの地に魅せられ住み着いたのだという。
構図も色彩もきれいなはずだ。
さらに、驚嘆に値するのは登場人物が1人の女優をのぞいてすべて、そこに住む信仰心の厚い敬虔な人々だということである。
どうみても素人には見えない。自然体で、表情や顔が生きる力にあふれ、とぎすまされている。過酷な自然と共に生きると、こうした良い顔になれるのかと思う。
しかも、現在でもキャラバンは続けられているらしい。
生きるためにヤクに塩を積んでヒマラヤを越え、穀物にかえ交易して暮らしているというのだ。
村の人から長老とあがめられ、若い頃キャラバンの隊長をつとめてきた人物の息子が死んだ。キャラバン隊長という絶対の権力を譲った息子亡き今、その地位をどうするか。
息子の親友で長老とかつて対立していた男が周囲の信頼を得て隊長になった。しかし、進歩的で合理的な彼の考え方を長老は気に入らない。
まだ幼い孫に期待をかける長老は、無謀にも自分でキャラバンを出すことにする。
2人の対立は何を生むのか。
村はどうなるのか。
撮影は5000メートルを超えるネパール山中で、およそ8カ月をかけて行われた。
ここで見られるのは厳しい自然だけではない。ワンシーンごとの映像が、絵のように完成されている。
黄色い麦畑とヒマラヤ。
キャラバンの牛の群。
ベージュ色の地面に朱色の衣、そして、ターバン。
それもそのはず、長編第1作目というエリック・ヴァリ監督は、元はナショナル・ジオグラフィックの写真家だった。彼はこの地に魅せられ住み着いたのだという。
構図も色彩もきれいなはずだ。
さらに、驚嘆に値するのは登場人物が1人の女優をのぞいてすべて、そこに住む信仰心の厚い敬虔な人々だということである。
どうみても素人には見えない。自然体で、表情や顔が生きる力にあふれ、とぎすまされている。過酷な自然と共に生きると、こうした良い顔になれるのかと思う。
しかも、現在でもキャラバンは続けられているらしい。
生きるためにヤクに塩を積んでヒマラヤを越え、穀物にかえ交易して暮らしているというのだ。
2006年08月23日
アンジェラの灰
1997年ピュリツァー賞を受賞し、欧米で600万部の大ベストセラーとなった同名ドキュメンタリーの映画化。
1930年代、アイルランドからの移民としてニューヨークで暮らすマコート一家。若い夫妻には4人の幼い男の子と生まれたばかりの女の子がいた。
不況で父親に仕事はなく、彼は失業手当まで呑んでしまうほどの酒好きだった。食べるものもなく、ある日、小さな女の子は死んでしまう。悲しみにくれる母親は、故郷の家族を頼ろうと、一家でアイルランドに戻る。
アイルランドに戻っても、父親は働かなかった。働いてもすぐにクビになり、失業手当は酒代に消えた。ここで、下の双子の男の子が次々に亡くなる。そして、また子どもが生まれる。父親に対して、妻も子どもたちも呆れているが、憎み突き放すことはできない。
映画を見ながら、エミール・ゾラの小説「居酒屋」を思い出した。「居酒屋」は、だんながヤクザな男だったため、娼婦にまで身をやつす女の物語である。
男にほれ、情、母性が仇となって不幸になる女性は多い。逆に、呑む、打つ、買うといった遊びにうつつをぬかし、女性や家族を不幸の泥沼に引きずり込む男も多い。
女の愚かさと男のずるさ。
これは、男と女の悪しき業ともいえるだろう。アンジェラの灰は、この業を見るものに突きつける。
やましいところのある人は、そら恐ろしい気持ちになるにちがいない。
この映画は、主人公フランクが、少年から青年へと育つ成長談である。
フランクは、どんなに悲惨な状況でも、子どもらしく伸び伸びとしている。随所に、ウイットに富んだエピソードがちりばめられており、笑いを誘う。
健康な男の子の関心といえば、異性であり、性であるが、それも牧歌的な楽しい話ばかり。また、アイルランドでは、キリスト教のカトリックの教えが徹底されているようだが、フランクの自然な発想は、カトリックの厳格な教えを説く教師たちをハッとさせたりする。
また、この映画では、社会の最底辺に暮らす庶民の生活が丹念に描かれている。街並み、食べるもの、着るもの、部屋、トイレまで、街の息づかいがこまやかに伝わってくるようだ。
庶民への温かな視点をもった作品だ。
ニューヨークでも、アイルランドでも、食べるものがないとき、近所のやさしいおばさんが助けてくれたりする。
何とも言えない郷愁を誘う作品だ。
1930年代、アイルランドからの移民としてニューヨークで暮らすマコート一家。若い夫妻には4人の幼い男の子と生まれたばかりの女の子がいた。
不況で父親に仕事はなく、彼は失業手当まで呑んでしまうほどの酒好きだった。食べるものもなく、ある日、小さな女の子は死んでしまう。悲しみにくれる母親は、故郷の家族を頼ろうと、一家でアイルランドに戻る。
アイルランドに戻っても、父親は働かなかった。働いてもすぐにクビになり、失業手当は酒代に消えた。ここで、下の双子の男の子が次々に亡くなる。そして、また子どもが生まれる。父親に対して、妻も子どもたちも呆れているが、憎み突き放すことはできない。
映画を見ながら、エミール・ゾラの小説「居酒屋」を思い出した。「居酒屋」は、だんながヤクザな男だったため、娼婦にまで身をやつす女の物語である。
男にほれ、情、母性が仇となって不幸になる女性は多い。逆に、呑む、打つ、買うといった遊びにうつつをぬかし、女性や家族を不幸の泥沼に引きずり込む男も多い。
女の愚かさと男のずるさ。
これは、男と女の悪しき業ともいえるだろう。アンジェラの灰は、この業を見るものに突きつける。
やましいところのある人は、そら恐ろしい気持ちになるにちがいない。
この映画は、主人公フランクが、少年から青年へと育つ成長談である。
フランクは、どんなに悲惨な状況でも、子どもらしく伸び伸びとしている。随所に、ウイットに富んだエピソードがちりばめられており、笑いを誘う。
健康な男の子の関心といえば、異性であり、性であるが、それも牧歌的な楽しい話ばかり。また、アイルランドでは、キリスト教のカトリックの教えが徹底されているようだが、フランクの自然な発想は、カトリックの厳格な教えを説く教師たちをハッとさせたりする。
また、この映画では、社会の最底辺に暮らす庶民の生活が丹念に描かれている。街並み、食べるもの、着るもの、部屋、トイレまで、街の息づかいがこまやかに伝わってくるようだ。
庶民への温かな視点をもった作品だ。
ニューヨークでも、アイルランドでも、食べるものがないとき、近所のやさしいおばさんが助けてくれたりする。
何とも言えない郷愁を誘う作品だ。
2006年08月22日
十五才 学校IV
不登校、学級崩壊、いじめ……そういった顕在化した問題をあげるまでもなく、思春期の子どもの想いを理解するのは難しい。
親は価値観を押しつけてはいないだろうか。周りの大人たちは何を見せればよいのか。深く考えさせられる作品だ。
横浜郊外に住む中学3年の大介(金井勇太)は、学校に通わなくなって半年がたつ。
ある日、両親に内証で九州の屋久島に縄文杉を見に行こうと決心し、ヒッチハイクをはじめる。果たして彼は、無事に遠い屋久島にたどり着くことができるのだろうか――。
大介は、旅を通じて大きく成長していく。見たことがない景色を見、いろいろな人の人生と接し、人生の悲しみやつらさを断片的ではあるが知ることになる。
そして、樹齢7000年の縄文杉に会ってエネルギーをもらいたいという夢を成し遂げることによって得る達成感。
つまらない人間だと思っていた自分だって、やり遂げることができるのだという自信がわいてくる。
作品中にでてくる詩がいい。
「――早く着くことなんか目的じゃないんだ。雲より遅くてじゅうぶんさ。この星が浪人にくれるものを見逃したくないんだ。――」
つい早いことが重要だと思ってしまいがちだ。
しかし、本当にそうだろうか。
立ち止まって、ゆっくり辺りを見回すことによって得られるものも多いはずだ。
今、大人が子どもたちにできることは、寛大な心で見守ること。
人間は自分を大切にし、愛し愛されるところからすべてがはじまるのだということを教えること。
そして、生きる姿を素直に見せることだろう。
大人が一生懸命に生きていさえすれば、その姿から学ぶことは多いはずだ。そのためにもまず、大人自身が居住まいを正し、自信をもった生き方をしなくてはならない。
学校シリーズも4本目になるが、それぞれが味わい深い。この作品もまた、山田洋次監督の愛が感じられる作品になっている。
親は価値観を押しつけてはいないだろうか。周りの大人たちは何を見せればよいのか。深く考えさせられる作品だ。
横浜郊外に住む中学3年の大介(金井勇太)は、学校に通わなくなって半年がたつ。
ある日、両親に内証で九州の屋久島に縄文杉を見に行こうと決心し、ヒッチハイクをはじめる。果たして彼は、無事に遠い屋久島にたどり着くことができるのだろうか――。
大介は、旅を通じて大きく成長していく。見たことがない景色を見、いろいろな人の人生と接し、人生の悲しみやつらさを断片的ではあるが知ることになる。
そして、樹齢7000年の縄文杉に会ってエネルギーをもらいたいという夢を成し遂げることによって得る達成感。
つまらない人間だと思っていた自分だって、やり遂げることができるのだという自信がわいてくる。
作品中にでてくる詩がいい。
「――早く着くことなんか目的じゃないんだ。雲より遅くてじゅうぶんさ。この星が浪人にくれるものを見逃したくないんだ。――」
つい早いことが重要だと思ってしまいがちだ。
しかし、本当にそうだろうか。
立ち止まって、ゆっくり辺りを見回すことによって得られるものも多いはずだ。
今、大人が子どもたちにできることは、寛大な心で見守ること。
人間は自分を大切にし、愛し愛されるところからすべてがはじまるのだということを教えること。
そして、生きる姿を素直に見せることだろう。
大人が一生懸命に生きていさえすれば、その姿から学ぶことは多いはずだ。そのためにもまず、大人自身が居住まいを正し、自信をもった生き方をしなくてはならない。
学校シリーズも4本目になるが、それぞれが味わい深い。この作品もまた、山田洋次監督の愛が感じられる作品になっている。
2006年08月21日
X-MEN
冒頭、ポーランドのナチスの強制収容所で、ユダヤ人の男の子が、両親から引き裂かれるシーンが映る。両親と別れたくない男の子は、泣き叫ぶ。少年の強烈な“思い”は、鉄の扉をグシャグシャに変形させてしまう。
原作は、1960年代の伝説的な人気のアメリカン・コミック。見る前のイメージは、単純なアクション大作だったが、非常にテーマが深く、ただの実写版ではない。
X-MENとは、いわゆる“超能力”をもったミュータントと呼ばれるごく少数の新しい人類だ。彼らは、進化によって超能力をもっているのだが、大多数の旧人類から危険視され、疎外されている。この映画は、異質なものを排除してしまう、人類がもつ“差別”という病を描いている。
物語は、三者の対立が軸となる。
ミュータントを排除しようとする人類。
そうした人類を支配しようとするミュータント。
人間との共存を信じるミュータントだ。
そして、対立するミュータント同士が、さまざまな超能力を駆使して相争う。
人類を支配しようとするミュータントのボス・マグニートーは、冒頭の少年が年老いたという設定である。マグニートーの論理は、自分たちを差別する者を攻撃しようとするもの。この論理は、差別される側からすれば、当たり前かもしれない。
一方、旧人類との共存は可能だと信じるチャールズもいる。
ミュータントへの人種差別を描いているが、60年代、アメリカに起こった公民権運動が背景にあることは想像にかたくない。
どこまで人間を信じることができるのか。
マグニートーは、到底信じない。
チャールズは、どんな偏屈な人間であろうと、まずは信じる。
ここに、両者の人間観が現れている。
果たして、見る側の自分はどちらの人間だろうか。
もちろん、アクション・シーンは見応え十分だ。超能力と白兵戦をうまくミックスしており、心臓をドキドキバクバクさせる迫力にあふれている。
主人公のウルヴァリン役を演じたオーストラリアの男優ヒュー・ジャックマンは、ハリウッド初出演。男臭いが、脂ぎってはいない。変な自己主張を感じさせない、なかなかにいい俳優だと思った。
原作は、1960年代の伝説的な人気のアメリカン・コミック。見る前のイメージは、単純なアクション大作だったが、非常にテーマが深く、ただの実写版ではない。
X-MENとは、いわゆる“超能力”をもったミュータントと呼ばれるごく少数の新しい人類だ。彼らは、進化によって超能力をもっているのだが、大多数の旧人類から危険視され、疎外されている。この映画は、異質なものを排除してしまう、人類がもつ“差別”という病を描いている。
物語は、三者の対立が軸となる。
ミュータントを排除しようとする人類。
そうした人類を支配しようとするミュータント。
人間との共存を信じるミュータントだ。
そして、対立するミュータント同士が、さまざまな超能力を駆使して相争う。
人類を支配しようとするミュータントのボス・マグニートーは、冒頭の少年が年老いたという設定である。マグニートーの論理は、自分たちを差別する者を攻撃しようとするもの。この論理は、差別される側からすれば、当たり前かもしれない。
一方、旧人類との共存は可能だと信じるチャールズもいる。
ミュータントへの人種差別を描いているが、60年代、アメリカに起こった公民権運動が背景にあることは想像にかたくない。
どこまで人間を信じることができるのか。
マグニートーは、到底信じない。
チャールズは、どんな偏屈な人間であろうと、まずは信じる。
ここに、両者の人間観が現れている。
果たして、見る側の自分はどちらの人間だろうか。
もちろん、アクション・シーンは見応え十分だ。超能力と白兵戦をうまくミックスしており、心臓をドキドキバクバクさせる迫力にあふれている。
主人公のウルヴァリン役を演じたオーストラリアの男優ヒュー・ジャックマンは、ハリウッド初出演。男臭いが、脂ぎってはいない。変な自己主張を感じさせない、なかなかにいい俳優だと思った。
2006年08月20日
スペースカウボーイ
クリント・イーストウッド監督=主演作品。
1958年、米ソのあいだで熾烈な宇宙開発競争が展開されているなか、空軍の選り抜きパイロットで構成された“チーム・ダイダロス”は日夜、宇宙飛行士になるための激しい訓練を繰り広げていた。
ところが、突然プロジェクトの権限が新しく設立されたNASA(アメリカ航空宇宙局)に移行し、アメリカ人初の宇宙飛行士になるという4人のメンバーの願いは夢と消えた。
ところが、それから40年の時を経て、彼らにチャンスが訪れる。
旧ソ連の通信衛星が故障し、地球に落下する危険性が高いとの知らせがメンバーの1人コービン(イーストウッド)に届く。
その衛星はかつて彼が設計したシステムを使用しており、彼の協力が必要だったのだ。
コービンは提案する。もしも“チーム・ダイダロス”を復活させて、宇宙に修理に向かわせてくれるなら協力しよう……。
こうして、この映画は老人パワー全開となるのだが、周囲は老人たちを優しくいたわってはくれない。むしろ若いエリートパイロットたちは、どうして今頃こんな老いぼれが出てくるのだと冷ややかな態度だ。
ところが、イーストウッドやトミー・リー・ジョーンズら演じる個性派ぞろいの老人パイロットたちにいたわりなど必要ない。体力や俊敏性は衰えていても、コンピューター世代に太刀打ちできない手作業的技術を身につけているし、女性を口説くユーモアや老練なテクニックにおいて絶対に若い連中に負けていない。この映画は老いについての新鮮な解釈を提案してくれている。
また、アメリカと日本ではこんなに“チームワーク”についての考えや理想が違うものか、とあらためて感心させられた。
メンバーがエゴを捨てチームに献身するのが日本的だとすると、アメリカではむしろ個々のメンバーのエゴを前面に出し、その熾烈な衝突を経て、チームがより高い段階に達することが理想とされる。
本作の成功もまた、メンバーの個性を最大限に重視して全体としての力の向上を目指すアメリカ的理想が有効に機能した結果で、イーストウッド個人だけでなく、明らかにチームワークの勝利なのだ。
1958年、米ソのあいだで熾烈な宇宙開発競争が展開されているなか、空軍の選り抜きパイロットで構成された“チーム・ダイダロス”は日夜、宇宙飛行士になるための激しい訓練を繰り広げていた。
ところが、突然プロジェクトの権限が新しく設立されたNASA(アメリカ航空宇宙局)に移行し、アメリカ人初の宇宙飛行士になるという4人のメンバーの願いは夢と消えた。
ところが、それから40年の時を経て、彼らにチャンスが訪れる。
旧ソ連の通信衛星が故障し、地球に落下する危険性が高いとの知らせがメンバーの1人コービン(イーストウッド)に届く。
その衛星はかつて彼が設計したシステムを使用しており、彼の協力が必要だったのだ。
コービンは提案する。もしも“チーム・ダイダロス”を復活させて、宇宙に修理に向かわせてくれるなら協力しよう……。
こうして、この映画は老人パワー全開となるのだが、周囲は老人たちを優しくいたわってはくれない。むしろ若いエリートパイロットたちは、どうして今頃こんな老いぼれが出てくるのだと冷ややかな態度だ。
ところが、イーストウッドやトミー・リー・ジョーンズら演じる個性派ぞろいの老人パイロットたちにいたわりなど必要ない。体力や俊敏性は衰えていても、コンピューター世代に太刀打ちできない手作業的技術を身につけているし、女性を口説くユーモアや老練なテクニックにおいて絶対に若い連中に負けていない。この映画は老いについての新鮮な解釈を提案してくれている。
また、アメリカと日本ではこんなに“チームワーク”についての考えや理想が違うものか、とあらためて感心させられた。
メンバーがエゴを捨てチームに献身するのが日本的だとすると、アメリカではむしろ個々のメンバーのエゴを前面に出し、その熾烈な衝突を経て、チームがより高い段階に達することが理想とされる。
本作の成功もまた、メンバーの個性を最大限に重視して全体としての力の向上を目指すアメリカ的理想が有効に機能した結果で、イーストウッド個人だけでなく、明らかにチームワークの勝利なのだ。
2006年08月19日
英雄の条件
くせのある役をこなすことについては定評がある2大スター、トミー・リー・ジョーンズとサミュエル・L・ジャクソンの演技が見物である。
「逃亡者」で冷徹な連邦保安官役だったジョーンズは今回はアルコール依存症の海兵隊弁護士ヘイズ・ホッジス大佐を、「パルプフィクション」で哲学的な殺し屋を演じたジャクソンは海兵隊屈指の歴戦の勇士チルダーズ大佐を演じている。
中東イエメンでアメリカ大使館が大規模なデモ隊に包囲され、大使家族を救出することになる。
そのときチルダーズ率いる海兵隊は、銃撃で一般市民を80人も死亡させてしまう。世界中から人道主義を踏みにじる行為として非難され、アメリカの威信はどうなるのか。そのときとった行動は軍人として正しい選択だったのか。
チルダーズは軍事法廷で裁かれることになる。 テーマは忠誠心。
チルダーズはアメリカを愛し、誠実に海兵隊につくし、自分が正しいと信じたことを実行する真の軍人だ。
しかし、戦時下でとる行動を裁くのならそれはすべて殺人だ。人を殺すという行為はだれもが有罪なのは明白であるが、それが国を守るために敵を倒すという大義からなのか、それとも戦友を守るためなのか。さらに、そのために一般人を殺していいかとなると話は別である。
ベトナムでいっしょだったホッジスとは命をかけあった戦友。
人間として自信をなくしている3流弁護士ホッジスは、友の真実を見極めるためにイエメンに足を運ぶのだった。
“軍隊”をもたない日本の、戦争経験のない世代にも、軍人としてとるべき行動の是非が迫ってくる。
元アメリカ海軍長官だったジェームズ・ウエッブの原案をもとに脚本が作られ、ベトナムでのひとコマ、大使救出作戦の場面など、嘘のないように俳優たちに軍事教練したという。
ジャクソンが孤立無援の役柄を毅然として演じ、友情のために立ち上がる役を演じるジョーンズにしても、どんな個性のある役柄でも見事にこなす素晴らしい役者として印象に残る作品だと思う。
「逃亡者」で冷徹な連邦保安官役だったジョーンズは今回はアルコール依存症の海兵隊弁護士ヘイズ・ホッジス大佐を、「パルプフィクション」で哲学的な殺し屋を演じたジャクソンは海兵隊屈指の歴戦の勇士チルダーズ大佐を演じている。
中東イエメンでアメリカ大使館が大規模なデモ隊に包囲され、大使家族を救出することになる。
そのときチルダーズ率いる海兵隊は、銃撃で一般市民を80人も死亡させてしまう。世界中から人道主義を踏みにじる行為として非難され、アメリカの威信はどうなるのか。そのときとった行動は軍人として正しい選択だったのか。
チルダーズは軍事法廷で裁かれることになる。 テーマは忠誠心。
チルダーズはアメリカを愛し、誠実に海兵隊につくし、自分が正しいと信じたことを実行する真の軍人だ。
しかし、戦時下でとる行動を裁くのならそれはすべて殺人だ。人を殺すという行為はだれもが有罪なのは明白であるが、それが国を守るために敵を倒すという大義からなのか、それとも戦友を守るためなのか。さらに、そのために一般人を殺していいかとなると話は別である。
ベトナムでいっしょだったホッジスとは命をかけあった戦友。
人間として自信をなくしている3流弁護士ホッジスは、友の真実を見極めるためにイエメンに足を運ぶのだった。
“軍隊”をもたない日本の、戦争経験のない世代にも、軍人としてとるべき行動の是非が迫ってくる。
元アメリカ海軍長官だったジェームズ・ウエッブの原案をもとに脚本が作られ、ベトナムでのひとコマ、大使救出作戦の場面など、嘘のないように俳優たちに軍事教練したという。
ジャクソンが孤立無援の役柄を毅然として演じ、友情のために立ち上がる役を演じるジョーンズにしても、どんな個性のある役柄でも見事にこなす素晴らしい役者として印象に残る作品だと思う。
2006年08月18日
ホワイトアウト
真冬の新潟県、雪に覆われた日本最大のダムをテロリストが占拠する。
テロリストは、ダムの爆破による水害で国を脅し、50億円を要求。猛吹雪のため、だれもダムに近づくことができない。
ダムの職員が人質になるなか、ひとり自由の身の富樫(織田裕二)が、テロリストに挑んでいく。
この映画の最大の成功の因は、脚本にあると思う。
原作は、ベストセラーとなった同名小説。原作者の真保裕一が、自ら脚本を書いている。
見るものの予想を裏切り続ける物語展開は卓抜。なかでも、クライマックスのどんでん返しの連続が楽しい。
演出で「うまい!」と感じた点は、射殺シーンのクールさ。
こうしたシーンは、どうしても嘘臭くなりがちだが、ここをさらっと描いたところに好感がもてる。
キャスティングもなかなか良い。
特に、テロリストの首領の佐藤浩市がはまり役だ。もともと演技力のある役者だが、癖のある難しい役を自然に演じている。
ほかの役者も、変に主張していない。キャスティングがそれぞれにマッチしたと言える。多少、ん!? と感じるような人はいるが、許せる範囲だろう。
さて、この映画をジャンル分けするとしたら、アクション映画になるのだろうか。もともと設定が“ダム”ということもあって、A・シュワルツェネッガーの主演作品などと比べれば、それほど派手とは言えない。むしろ、銃撃戦や白兵戦などの緊張感を楽しむべきだろう。
感心したのは、キャラクターの設定。
主人公の富樫は、雪山で友人の吉岡(石黒賢)を亡くしている。吉岡は、「もし、自分の身に何かあったときは、婚約者の千晶(松嶋菜々子)を守ってくれ」と告げていた。千晶は、テロリストの人質となっている。富樫は、千晶と会ったことはない。
恋人や妻のために頑張るヒーローは山ほどいるが、亡くなった男の友情のために命をかけるというキャラクターはちょっといない。ここまで純粋な男の心には、男もほれる。ほれるとまではいかなくても、好感をもってしまう。このあたりに、原作及び脚本の真保裕一のうまさを感じた。そうです、ラストシーンは、ホロッとさせられます。
けっこう、ドキッとさせられるシーンもあるが、その効果音とBGMがまたいい。
テロリストは、ダムの爆破による水害で国を脅し、50億円を要求。猛吹雪のため、だれもダムに近づくことができない。
ダムの職員が人質になるなか、ひとり自由の身の富樫(織田裕二)が、テロリストに挑んでいく。
この映画の最大の成功の因は、脚本にあると思う。
原作は、ベストセラーとなった同名小説。原作者の真保裕一が、自ら脚本を書いている。
見るものの予想を裏切り続ける物語展開は卓抜。なかでも、クライマックスのどんでん返しの連続が楽しい。
演出で「うまい!」と感じた点は、射殺シーンのクールさ。
こうしたシーンは、どうしても嘘臭くなりがちだが、ここをさらっと描いたところに好感がもてる。
キャスティングもなかなか良い。
特に、テロリストの首領の佐藤浩市がはまり役だ。もともと演技力のある役者だが、癖のある難しい役を自然に演じている。
ほかの役者も、変に主張していない。キャスティングがそれぞれにマッチしたと言える。多少、ん!? と感じるような人はいるが、許せる範囲だろう。
さて、この映画をジャンル分けするとしたら、アクション映画になるのだろうか。もともと設定が“ダム”ということもあって、A・シュワルツェネッガーの主演作品などと比べれば、それほど派手とは言えない。むしろ、銃撃戦や白兵戦などの緊張感を楽しむべきだろう。
感心したのは、キャラクターの設定。
主人公の富樫は、雪山で友人の吉岡(石黒賢)を亡くしている。吉岡は、「もし、自分の身に何かあったときは、婚約者の千晶(松嶋菜々子)を守ってくれ」と告げていた。千晶は、テロリストの人質となっている。富樫は、千晶と会ったことはない。
恋人や妻のために頑張るヒーローは山ほどいるが、亡くなった男の友情のために命をかけるというキャラクターはちょっといない。ここまで純粋な男の心には、男もほれる。ほれるとまではいかなくても、好感をもってしまう。このあたりに、原作及び脚本の真保裕一のうまさを感じた。そうです、ラストシーンは、ホロッとさせられます。
けっこう、ドキッとさせられるシーンもあるが、その効果音とBGMがまたいい。
2006年08月17日
マルコヴィッチの穴
原題は「BEING JOHN MALKOVICH」。つまり“ジョン・マルコヴィッチであること”。
マルコヴィッチとは90年代初めに『シェルタリング・スカイ』や『20日鼠と人間』などで頭角を現した本格派俳優。
この映画は“有名人になりたい病”を主題として扱っているが、その有名人が誰でも知っているディカプリオやトム・クルーズではなく、知ってる人なら知っているし、顔は知ってるが名前を知らなかったり、逆に名前は知ってるが顔は知らない人も多かったりするだろうマルコヴィッチをあえて選んだところに、ヒネリのきいた冴えがあると言える。
でもなぜ“穴”なのか?
物語の主人公は、才能には恵まれているが、なかなか成功できずに失意のどん底にある人形使いシュワルツ(J・キューザック)。
彼は妻(C・ディアス)の忠告に従って嫌々仕事を見つけるが、同じオフィス・ビルで働くマキシン(C・キーナー)に恋してしまう。ただし、彼女はほとんど相手にしてくれない。
ある日、そんな状況を一変させる出来事が起こる。偶然オフィスの一角に見つけた穴にシュワルツが入ってみると、驚くことに、15分だけマルコヴィッチの脳(?)に侵入し、あの有名人になることができたのだ!
シュワルツはマキシンと相談して、この穴を商売に使うことに決める。その後、マルコヴィッチ自身の抵抗にあったり、恋愛騒動が複雑さを増したり、物語は混迷の度合いを深めていく……。
このユニークな物語を見事に映画化したのは、スパイク・ジョーンズ。若きクリエーターだ。
天井をえらく低くして「不思議の国」じみたオフィス・ビルのセットを作らせたり、ディアスをノーメークで登場させたり……妥協を知らない完全主義ぶりを発揮して、今後の活躍を大いに期待させる。
マルコヴィッチとは90年代初めに『シェルタリング・スカイ』や『20日鼠と人間』などで頭角を現した本格派俳優。
この映画は“有名人になりたい病”を主題として扱っているが、その有名人が誰でも知っているディカプリオやトム・クルーズではなく、知ってる人なら知っているし、顔は知ってるが名前を知らなかったり、逆に名前は知ってるが顔は知らない人も多かったりするだろうマルコヴィッチをあえて選んだところに、ヒネリのきいた冴えがあると言える。
でもなぜ“穴”なのか?
物語の主人公は、才能には恵まれているが、なかなか成功できずに失意のどん底にある人形使いシュワルツ(J・キューザック)。
彼は妻(C・ディアス)の忠告に従って嫌々仕事を見つけるが、同じオフィス・ビルで働くマキシン(C・キーナー)に恋してしまう。ただし、彼女はほとんど相手にしてくれない。
ある日、そんな状況を一変させる出来事が起こる。偶然オフィスの一角に見つけた穴にシュワルツが入ってみると、驚くことに、15分だけマルコヴィッチの脳(?)に侵入し、あの有名人になることができたのだ!
シュワルツはマキシンと相談して、この穴を商売に使うことに決める。その後、マルコヴィッチ自身の抵抗にあったり、恋愛騒動が複雑さを増したり、物語は混迷の度合いを深めていく……。
このユニークな物語を見事に映画化したのは、スパイク・ジョーンズ。若きクリエーターだ。
天井をえらく低くして「不思議の国」じみたオフィス・ビルのセットを作らせたり、ディアスをノーメークで登場させたり……妥協を知らない完全主義ぶりを発揮して、今後の活躍を大いに期待させる。
2006年08月16日
ミュージック・オブ・ハート
ロベルタ(メリル・ストリープ)が音楽教師として、ニューヨークでも指折りの物騒な地域「イースト・ハーレム」の小学校に、50挺ものバイオリンを抱えて乗り込む。
悪ガキどもはバイオリンの弓でチャンバラをはじめる始末。しかし、ロベルタの率直な人柄に心を開き、子どもたちは鋭敏な力を発揮してグングン上達していく。
やがて、発表会で「キラキラ星」を見事に合奏する我が子の誇らしげな姿に、親の目に涙が光る。
果ては、スターンやパールマンら世界的なバイオリニストと、カーネギーホールで協演することになるのだ!
しかし、このドラマは単なる美談とは一線を画している。
ある日、練習熱心な少年が来ない。母に“行くな”といわれたからだ。
母は、ロベルタを非難する。「頼みもしないのに、スラムの子どもを救う気で乗り込んでくる白人教師が前にもいた」と。
ロベルタも黙ってはいない。「誰を救う気もない。これは自分の子どもを養うために必要な仕事」「あなたは知ってるの? バイオリンを弾いているとき、あなたの息子が輝いているのを」――と。
ロベルタは夫に逃げられ、ふたりの息子を抱えて働き口を見つけねばならなかった。
職場で直面する、人種差別の深い溝。“家族が殺された”と子どもが休むスラムの現実……。家庭では、思春期の息子との葛藤。頼れる夫のいない不安……。それでも、ロベルタは突き進む。音楽への純粋な愛を鼓舞し、子どもたちへの愛と喜ぶ顔に支えられながら――。ありのままの自分をさらけ出し、教師として母として、やるべきことを成し遂げていくひたむきな姿は、美しく、清々しい。
ロベルタは下見でカーネギーホールの舞台に立つ。
劇場を満たしている静寂と圧倒的な威厳がスクリーンから伝わってくる。
そこで、バイオリンの巨匠であり、音楽の殿堂・カーネギーホールの総館長であるアイザック・スターンがロベルタに語る。
「チャイコフスキーもハイフェッツも、ラフマニノフも皆、ここに立つ人を歓迎してくれる。君たちもここの一員だよ」と。
悪ガキどもはバイオリンの弓でチャンバラをはじめる始末。しかし、ロベルタの率直な人柄に心を開き、子どもたちは鋭敏な力を発揮してグングン上達していく。
やがて、発表会で「キラキラ星」を見事に合奏する我が子の誇らしげな姿に、親の目に涙が光る。
果ては、スターンやパールマンら世界的なバイオリニストと、カーネギーホールで協演することになるのだ!
しかし、このドラマは単なる美談とは一線を画している。
ある日、練習熱心な少年が来ない。母に“行くな”といわれたからだ。
母は、ロベルタを非難する。「頼みもしないのに、スラムの子どもを救う気で乗り込んでくる白人教師が前にもいた」と。
ロベルタも黙ってはいない。「誰を救う気もない。これは自分の子どもを養うために必要な仕事」「あなたは知ってるの? バイオリンを弾いているとき、あなたの息子が輝いているのを」――と。
ロベルタは夫に逃げられ、ふたりの息子を抱えて働き口を見つけねばならなかった。
職場で直面する、人種差別の深い溝。“家族が殺された”と子どもが休むスラムの現実……。家庭では、思春期の息子との葛藤。頼れる夫のいない不安……。それでも、ロベルタは突き進む。音楽への純粋な愛を鼓舞し、子どもたちへの愛と喜ぶ顔に支えられながら――。ありのままの自分をさらけ出し、教師として母として、やるべきことを成し遂げていくひたむきな姿は、美しく、清々しい。
ロベルタは下見でカーネギーホールの舞台に立つ。
劇場を満たしている静寂と圧倒的な威厳がスクリーンから伝わってくる。
そこで、バイオリンの巨匠であり、音楽の殿堂・カーネギーホールの総館長であるアイザック・スターンがロベルタに語る。
「チャイコフスキーもハイフェッツも、ラフマニノフも皆、ここに立つ人を歓迎してくれる。君たちもここの一員だよ」と。
2006年08月15日
ザ・ハリケーン
先日紹介した「エリン・ブロコビッチ」と同じく、実話を題材にした作品。
壮大なアクションやファンタジー大作も小気味良いが、真実の話はそれとは違った感動を味わえる。今まで自分が知らなかった世界で、こんなにもたくましく、切なく生きた人々がいたのだという驚きが胸に迫ってくる。
1963年、黒人ボクサーのハリケーン(デンゼル・ワシントン)は、ウエルター級のチャンピオンにまで上り詰めていた。
華々しい戦績をあげる彼に突然、殺人事件の容疑がかけられる。裁判で無実を訴えるのだが終身刑が宣告されてしまう。
彼は、獄中でも無実を訴え続け、自伝を執筆して出版するやいなや大反響を呼び、ボブ・ディランやモハメッド・アリなどが釈放運動に加わってくれる。しかし、再審も有罪。ハリケーンは絶望し、社会とのかかわりをいっさい断つようになっていく。
古本市でハリケーンの自伝を何気なく手に取ったレズラは、ハリケーンの人生に共感を覚え、仲間と一緒にハリケーンの無罪を勝ち取るために、立ち上がるのだった……。
デンゼル・ワシントンはこの企画が始まった6年前からハリケーン役を切望していた。役にいどむために、27キロの減量とトレーニングを行い1年の準備期間をへてボクサー体形に自分の身体を鍛え上げたという。そのため、ボクシングのシーンも違和感なく受け入れることができる。
さらに、時の経過と共に、ワシントンのまなざしが変わってくるところも見物だ。
無実の罪で投獄されたことに対する怒り、真実は必ず認められるはずだと信じてやまない姿、絶望、孤高の境地、レズラとかかわることによって得る安らぎ、そして信頼――ワシントンの入魂の一作といえそうだ。
壮大なアクションやファンタジー大作も小気味良いが、真実の話はそれとは違った感動を味わえる。今まで自分が知らなかった世界で、こんなにもたくましく、切なく生きた人々がいたのだという驚きが胸に迫ってくる。
1963年、黒人ボクサーのハリケーン(デンゼル・ワシントン)は、ウエルター級のチャンピオンにまで上り詰めていた。
華々しい戦績をあげる彼に突然、殺人事件の容疑がかけられる。裁判で無実を訴えるのだが終身刑が宣告されてしまう。
彼は、獄中でも無実を訴え続け、自伝を執筆して出版するやいなや大反響を呼び、ボブ・ディランやモハメッド・アリなどが釈放運動に加わってくれる。しかし、再審も有罪。ハリケーンは絶望し、社会とのかかわりをいっさい断つようになっていく。
古本市でハリケーンの自伝を何気なく手に取ったレズラは、ハリケーンの人生に共感を覚え、仲間と一緒にハリケーンの無罪を勝ち取るために、立ち上がるのだった……。
デンゼル・ワシントンはこの企画が始まった6年前からハリケーン役を切望していた。役にいどむために、27キロの減量とトレーニングを行い1年の準備期間をへてボクサー体形に自分の身体を鍛え上げたという。そのため、ボクシングのシーンも違和感なく受け入れることができる。
さらに、時の経過と共に、ワシントンのまなざしが変わってくるところも見物だ。
無実の罪で投獄されたことに対する怒り、真実は必ず認められるはずだと信じてやまない姿、絶望、孤高の境地、レズラとかかわることによって得る安らぎ、そして信頼――ワシントンの入魂の一作といえそうだ。
2006年08月14日
サイダーハウス・ルール
ラッセ・ハルストレム監督の作品といえば、子供を見つめるまなざしが温かいことで定評がある。
しかも、原作は「ガープの世界」「ホテル・ニューハンプシャー」などの作品で知られるアメリカ現代文学の巨匠ジョン・アーヴィング。彼自身が13年もの歳月を費やして脚色し、映画化した。
原作者が脚色をすると、原作への思い入れが強すぎて映画としてはわかりにくいものになりがちだが、このベストセラー作家は違った。
そのエキスを抜き取り、一人の青年の成長を描く感動のドラマに仕上げている。
2000年度のアカデミー作品賞、監督賞など7部門にノミネートされ、最優秀助演男優賞と最優秀脚色賞を受賞した。
舞台は1930~40年ごろの孤児院。
ここで生まれ育ったホーマー・ウェルズ(トビー・マグワイヤ)は、ラーチ院長(マイケル・ケイン)に「人の役に立つ存在になれ」といわれ続けて大きくなった。
院長の掌中の玉のような存在だったホーマーもいつしか、外の世界に憧れて旅立つことを決心する。
外の世界は、見たことのないモノばかりだった。初めての海、口にしたことのないロブスター、野外で映画が見られるドライブインシアター。
そして、友情や甘い恋、悲しみ……人とのふれあいを通して今まで味わったことのない感情を味わい、一歩ずつ大人になっていく。
映像が詩的で美しい。
全体の色彩が抑制され灰色に近い田舎の風景。それが、作品の雰囲気にピッタリとマッチしている。
また、孤児院の子どもたちがいい。かわいらしく純粋なのだが、どこか孤独が感じられる。
人間は決して完ぺきでもなんでもない。
愚かで、たくさんの間違いや失敗を繰り返すが、小さな幸せを見つけて一生懸命に生きている。
人間への温かいまなざしと、深い愛が感じられる作品だ。
しかも、原作は「ガープの世界」「ホテル・ニューハンプシャー」などの作品で知られるアメリカ現代文学の巨匠ジョン・アーヴィング。彼自身が13年もの歳月を費やして脚色し、映画化した。
原作者が脚色をすると、原作への思い入れが強すぎて映画としてはわかりにくいものになりがちだが、このベストセラー作家は違った。
そのエキスを抜き取り、一人の青年の成長を描く感動のドラマに仕上げている。
2000年度のアカデミー作品賞、監督賞など7部門にノミネートされ、最優秀助演男優賞と最優秀脚色賞を受賞した。
舞台は1930~40年ごろの孤児院。
ここで生まれ育ったホーマー・ウェルズ(トビー・マグワイヤ)は、ラーチ院長(マイケル・ケイン)に「人の役に立つ存在になれ」といわれ続けて大きくなった。
院長の掌中の玉のような存在だったホーマーもいつしか、外の世界に憧れて旅立つことを決心する。
外の世界は、見たことのないモノばかりだった。初めての海、口にしたことのないロブスター、野外で映画が見られるドライブインシアター。
そして、友情や甘い恋、悲しみ……人とのふれあいを通して今まで味わったことのない感情を味わい、一歩ずつ大人になっていく。
映像が詩的で美しい。
全体の色彩が抑制され灰色に近い田舎の風景。それが、作品の雰囲気にピッタリとマッチしている。
また、孤児院の子どもたちがいい。かわいらしく純粋なのだが、どこか孤独が感じられる。
人間は決して完ぺきでもなんでもない。
愚かで、たくさんの間違いや失敗を繰り返すが、小さな幸せを見つけて一生懸命に生きている。
人間への温かいまなざしと、深い愛が感じられる作品だ。
2006年08月12日
エリン・ブロコビッチ
豪快ママのサクセスストーリー。
物語が実話であるだけに、人間捨てたもんじゃないなと妙に納得させられる。
エリンは2度結婚をし、2度別れ、子供が3人いる子連れの母親。悪いことに学歴も、経験も、職もない。
きょうの食費にも事欠き、職探しの毎日だが不運は続くもので、面接で落とされ落ち込んでいるときに車に追突される。弁護士に依頼するがあっけなく敗北。現実は厳しい。
行き詰まったエリンは自分が頼んだ弁護士事務所に押し掛け事務員として働きはじめる。
ファイルの整理をしていると気になる資料が出てきた。不動産関係の資料なのに、健康診断書や血液検査の結果が添付されていたのだ。
それを調査させてくれるようボスに願い出る。そして、隠された事実を暴き出すことになるのだ。
1歳にもならない乳飲み子と小学生の子供2人を抱え、働くママは一生懸命だ。
でも、おかしいと思ったことに突き進む勇気があり、理不尽は許さない。しかも、相手の立場にたって物事を考えることができる優しさがある。
その迫力と元気に圧倒される。
モデルになったエリン自身、学生時代ミスコンの女王になったと聞かされれば、エリン役がジュリア・ロバーツでもうなずける。
男なら、エリンのファッションにも目を奪われるはず。
本物のエリンのファッションに忠実に、20センチのミニスカート、7.5センチのヒール、胸元が大きくあいた身体にフィットしたシャツに身を包み、そこからゴージャスなボディーが弾け出る。
誰に何を言われても、自分が似合うと思ったものを、着たいときに着るという根性が生き方をなぞっている。ジュリアのスタイルとファッションと元気を見ているだけで、こちらまで元気づけられる爽快な作品だ。
エリン・ブロコビッチは、アメリカではだれもが知っている史上最高額の和解金を手にしたスーパー・ヒロイン。
いつでも元気で明るい彼女は、みんなの憧れになっている。やる気と根性と粘り強さがあれば、何も持っていなくても必ず成功を手に入れられるということを実践してくれたのだから。
彼女を見て、明日への活力をわかせたい。
物語が実話であるだけに、人間捨てたもんじゃないなと妙に納得させられる。
エリンは2度結婚をし、2度別れ、子供が3人いる子連れの母親。悪いことに学歴も、経験も、職もない。
きょうの食費にも事欠き、職探しの毎日だが不運は続くもので、面接で落とされ落ち込んでいるときに車に追突される。弁護士に依頼するがあっけなく敗北。現実は厳しい。
行き詰まったエリンは自分が頼んだ弁護士事務所に押し掛け事務員として働きはじめる。
ファイルの整理をしていると気になる資料が出てきた。不動産関係の資料なのに、健康診断書や血液検査の結果が添付されていたのだ。
それを調査させてくれるようボスに願い出る。そして、隠された事実を暴き出すことになるのだ。
1歳にもならない乳飲み子と小学生の子供2人を抱え、働くママは一生懸命だ。
でも、おかしいと思ったことに突き進む勇気があり、理不尽は許さない。しかも、相手の立場にたって物事を考えることができる優しさがある。
その迫力と元気に圧倒される。
モデルになったエリン自身、学生時代ミスコンの女王になったと聞かされれば、エリン役がジュリア・ロバーツでもうなずける。
男なら、エリンのファッションにも目を奪われるはず。
本物のエリンのファッションに忠実に、20センチのミニスカート、7.5センチのヒール、胸元が大きくあいた身体にフィットしたシャツに身を包み、そこからゴージャスなボディーが弾け出る。
誰に何を言われても、自分が似合うと思ったものを、着たいときに着るという根性が生き方をなぞっている。ジュリアのスタイルとファッションと元気を見ているだけで、こちらまで元気づけられる爽快な作品だ。
エリン・ブロコビッチは、アメリカではだれもが知っている史上最高額の和解金を手にしたスーパー・ヒロイン。
いつでも元気で明るい彼女は、みんなの憧れになっている。やる気と根性と粘り強さがあれば、何も持っていなくても必ず成功を手に入れられるということを実践してくれたのだから。
彼女を見て、明日への活力をわかせたい。
2006年08月11日
バットマン ビギンズ
サイコスリラーの秀作「メメント」「インソムニア」などを監督した、新進気鋭の映像作家であるクリストファー・ノーラン監督による「バットマン ビギンズ」。
本作では、バットマンの誕生秘話や、バットマンがゴッサム・シティの「闇の騎士」になるまでを追っている。
これまでスクリーンで語られなかった、ブルース・ウェインがいかにしてバットマンになったか、というバックグラウンドが初めて明かされる。
不気味な分身を生み出すために、彼がなぜ、どうやって戦闘力を身につけ、バットマンツールを手にしていったのかが……。
バットマン=B・ウェインを演じるクリスチャン・ベールは、これまでで最高にクールで、現代的、孤独なヒーロー像を築いている。
とりわけウェインが、自分の分身としてのバットマンのイメージ戦略を練る所は広告代理店そのもの。
バットモービルやコウモリ型のロゴマークを考案するあたりの、フェティッシュな物への偏愛ぶり、なんでも黒に塗りたがる色へのこだわりぶりは、ベールの出世作「アメリカン・サイコ」を思い出させて、面白い場面となっている。
そして、数々の特殊装置の開発を手助けするのが、ウェイン社開発部門に勤務するフォックス(モーガン・フリーマン)だ。
彼が生真面目な調子で、中国にバットマンマスクを発注したり、まるでドラえもんのように、次々とバットマンツールを作り出す様子が楽しい。
最初にコミックに登場してから60年余り、アメリカン・カルチャーの象徴でもある「バットマン」。
思いきり現代的な味付けで明かされる謎の、不思議なリアリティーが絶妙だ。
本作では、バットマンの誕生秘話や、バットマンがゴッサム・シティの「闇の騎士」になるまでを追っている。
これまでスクリーンで語られなかった、ブルース・ウェインがいかにしてバットマンになったか、というバックグラウンドが初めて明かされる。
不気味な分身を生み出すために、彼がなぜ、どうやって戦闘力を身につけ、バットマンツールを手にしていったのかが……。
バットマン=B・ウェインを演じるクリスチャン・ベールは、これまでで最高にクールで、現代的、孤独なヒーロー像を築いている。
とりわけウェインが、自分の分身としてのバットマンのイメージ戦略を練る所は広告代理店そのもの。
バットモービルやコウモリ型のロゴマークを考案するあたりの、フェティッシュな物への偏愛ぶり、なんでも黒に塗りたがる色へのこだわりぶりは、ベールの出世作「アメリカン・サイコ」を思い出させて、面白い場面となっている。
そして、数々の特殊装置の開発を手助けするのが、ウェイン社開発部門に勤務するフォックス(モーガン・フリーマン)だ。
彼が生真面目な調子で、中国にバットマンマスクを発注したり、まるでドラえもんのように、次々とバットマンツールを作り出す様子が楽しい。
最初にコミックに登場してから60年余り、アメリカン・カルチャーの象徴でもある「バットマン」。
思いきり現代的な味付けで明かされる謎の、不思議なリアリティーが絶妙だ。
2006年08月10日
亡国のイージス
福井晴敏の同名ベストセラー小説を、硬派な人間ドラマで定評のある阪本順治監督が映像化。そこに、真田広之、寺尾聰、佐藤浩市、中井貴一ら日本を代表する豪華俳優陣が結集。
物語は、海上自衛隊のイージス護衛艦「いそかぜ」が、テロリストたちに占拠されるところから始まる。
搭載されている特殊兵器の照準を東京に合わせ、日本政府にとてつもない要求を突きつける彼ら。
そこに立ち向かうのは、だれよりも艦の構造に詳しい先任伍長・仙石恒史(真田)だった……。
主演の真田は公開初日の舞台あいさつで「この『イージス』が僕らの手を離れて、大海原に漕ぎ出します。すべての思いを映画に込めました。観客の皆さまも(この作品の)クルーの一員として“世界平和”という向こう岸にたどり着くまで、一緒に漕ぎ続けていただければ」と語ったとか。
音楽と編集には、ハリウッドの第一線で活躍するスタッフを起用。
役者たちの熱演、そして海上自衛隊の初の全面協力も得て、邦画としては稀に見る、壮大なスケール感をもつエンターテインメント大作に仕上がっている。
一方で、考えさせられたのは、日本を守るはずの最新鋭システムが一瞬にして最強の凶器に変わる恐ろしさ。
それは、現実の世界でも起こりうる“落とし穴”かもしれない。
物語は、海上自衛隊のイージス護衛艦「いそかぜ」が、テロリストたちに占拠されるところから始まる。
搭載されている特殊兵器の照準を東京に合わせ、日本政府にとてつもない要求を突きつける彼ら。
そこに立ち向かうのは、だれよりも艦の構造に詳しい先任伍長・仙石恒史(真田)だった……。
主演の真田は公開初日の舞台あいさつで「この『イージス』が僕らの手を離れて、大海原に漕ぎ出します。すべての思いを映画に込めました。観客の皆さまも(この作品の)クルーの一員として“世界平和”という向こう岸にたどり着くまで、一緒に漕ぎ続けていただければ」と語ったとか。
音楽と編集には、ハリウッドの第一線で活躍するスタッフを起用。
役者たちの熱演、そして海上自衛隊の初の全面協力も得て、邦画としては稀に見る、壮大なスケール感をもつエンターテインメント大作に仕上がっている。
一方で、考えさせられたのは、日本を守るはずの最新鋭システムが一瞬にして最強の凶器に変わる恐ろしさ。
それは、現実の世界でも起こりうる“落とし穴”かもしれない。
2006年08月09日
ミッション・トゥ・マーズ
近未来には私たちにも、こんな体験ができるのでは……と、少年のころの冒険心を再び駆り立てられる作品。
監督は「ミッション:インポッシブル」で知られる鬼才ブライアン・デ・パルマ。
西暦2020年――。アポロ11号で初の月面着陸を果たしてから半世紀、人類はさらなる偉業を達成した。火星の有人探査である。
ルーク(ドン・チードル)率いる第1ミッションチームは、火星の地質に水の成分を発見。それは人類が火星で生活できるという可能性を示唆するものだった。しかし突然、彼らからの交信が途絶える。
かろうじて送られてきた最後の映像が物語るものは、ルーク以外の乗組員が全滅したとの悲劇的な事実だった。
ウッディ(ティム・ロビンス)を中心とした第2ミッションチームは、飛行士として優れた技量を備えたジム(ゲイリー・シニーズ)とともに、ルーク救出へと向かうのだが……。
探査船内部の居住スペースをはじめとする映像の数々は、米航空宇宙局(NASA)の全面的な協力を得て生み出され、自分もまた宇宙にいるのかと錯覚してしまうほどの現実感に富んでいる。
ストーリーはリアルなSFとしての前半に対し、後半はSFファンタジー的な様相を見せる。そこには、多くの人々が抱いた異星人との遭遇への憧れや、宇宙そのものへの畏敬の念が込められているように思えてならない。
ともあれ、彼ら飛行士たちの言動からは、危険をものともせず、己に課せられた任務を遂行しようとする責任感や使命感、同じ目的に向かって突き進む団結の大切さ、冒険を求め、新たな世界へと突き進む開拓精神――など、私たちの人生に即して学ぶべき点が多いばかりでなく、人間の持つ可能性の大きさにも気付かせてくれる。
宇宙飛行士として多くの謎に包まれた宇宙の真の姿を明らかにしたい――かつて、少年時代に描いた夢を思い起こさせてくれる、そんな作品だ。
監督は「ミッション:インポッシブル」で知られる鬼才ブライアン・デ・パルマ。
西暦2020年――。アポロ11号で初の月面着陸を果たしてから半世紀、人類はさらなる偉業を達成した。火星の有人探査である。
ルーク(ドン・チードル)率いる第1ミッションチームは、火星の地質に水の成分を発見。それは人類が火星で生活できるという可能性を示唆するものだった。しかし突然、彼らからの交信が途絶える。
かろうじて送られてきた最後の映像が物語るものは、ルーク以外の乗組員が全滅したとの悲劇的な事実だった。
ウッディ(ティム・ロビンス)を中心とした第2ミッションチームは、飛行士として優れた技量を備えたジム(ゲイリー・シニーズ)とともに、ルーク救出へと向かうのだが……。
探査船内部の居住スペースをはじめとする映像の数々は、米航空宇宙局(NASA)の全面的な協力を得て生み出され、自分もまた宇宙にいるのかと錯覚してしまうほどの現実感に富んでいる。
ストーリーはリアルなSFとしての前半に対し、後半はSFファンタジー的な様相を見せる。そこには、多くの人々が抱いた異星人との遭遇への憧れや、宇宙そのものへの畏敬の念が込められているように思えてならない。
ともあれ、彼ら飛行士たちの言動からは、危険をものともせず、己に課せられた任務を遂行しようとする責任感や使命感、同じ目的に向かって突き進む団結の大切さ、冒険を求め、新たな世界へと突き進む開拓精神――など、私たちの人生に即して学ぶべき点が多いばかりでなく、人間の持つ可能性の大きさにも気付かせてくれる。
宇宙飛行士として多くの謎に包まれた宇宙の真の姿を明らかにしたい――かつて、少年時代に描いた夢を思い起こさせてくれる、そんな作品だ。
2006年08月08日
ムッソリーニとお茶を
舞台は、ムッソリーニがいたころのイタリア・フィレンツェ。ストーリーは、コケティッシュでありながら、感動があり、さらに最後には驚きも味わえる。
少年ルカは、父親が愛人に産ませた子供であるため、秘書のメアリー(ジョーン・プローライト)に託される。
イギリス人であるメアリーの周りには個性的な外国の友人がたくさんいた。気位が高いイギリス人、レディ・ヘスター(マギー・スミス)は、亡き夫が大使だったことが誇りだ。
芸術家のアラベラ(ジュディ・デンチ)は、芸術の崇高さをルカに教え、メアリーはシェイクスピアの奥深さを学ばせる。
アメリカ人のエルサ(シェール)は、美貌を武器に富豪との結婚を繰り返し、高価な美術品を購入することが生きがいだ。
彼女はルカのために金銭的な後見人になってくれる。彼女たちに見守られながら成長するルカだが、時代はいつしか戦争に突入していくのだった。
流石、イタリア生まれの巨匠ゼフィレッリ監督だけあって、世界に名だたるウフィッツィ美術館の中での撮影も許可され、実にぜいたくな映像だ。
美術館の中で午後のお茶を楽しむ彼女たちの背景には美術の教科書に出てくるような名画の数々が見え隠れする。ドゥオモ(大聖堂)、ベッキオ橋、ミケランジェロのダビデ像の並ぶシニョーリア広場など、風景が丸ごと美術品のようで、さながら、イタリアの美の真髄を旅しているようである。
これが今月25日にDVD化され、自宅で見ることができる。贅沢の極みだろう。
彼女たちは、異邦人でありながらイタリアを心から愛している。
何より感激するのは、戦火の中、命がけで美しい物を守ろうとする場面である。
当時、実際に彼女たちのように美しい物を愛する人たちが必死で守ってくれたからこそ、人類の遺産とも言うべき芸術が現存しているのにちがいないのだ。愚かな人間の行為で破壊させず、死守してくれた方々に、我々は心から感謝しなければならない。
以下はネタバレになるが……。
物語の最後には、実はこの作品はゼフィレッリ監督の自伝的作品だということが明かされる。
作品中でメアリーと遊んだ“ロミオとジュリエットごっこ”は、ゼフィレッリの作品「ロミオとジュリエット」への伏線だったのだ。
ちょっとした遊び心と、しゃれっけとユーモアあふれる優しい作品に仕上がっている。
少年ルカは、父親が愛人に産ませた子供であるため、秘書のメアリー(ジョーン・プローライト)に託される。
イギリス人であるメアリーの周りには個性的な外国の友人がたくさんいた。気位が高いイギリス人、レディ・ヘスター(マギー・スミス)は、亡き夫が大使だったことが誇りだ。
芸術家のアラベラ(ジュディ・デンチ)は、芸術の崇高さをルカに教え、メアリーはシェイクスピアの奥深さを学ばせる。
アメリカ人のエルサ(シェール)は、美貌を武器に富豪との結婚を繰り返し、高価な美術品を購入することが生きがいだ。
彼女はルカのために金銭的な後見人になってくれる。彼女たちに見守られながら成長するルカだが、時代はいつしか戦争に突入していくのだった。
流石、イタリア生まれの巨匠ゼフィレッリ監督だけあって、世界に名だたるウフィッツィ美術館の中での撮影も許可され、実にぜいたくな映像だ。
美術館の中で午後のお茶を楽しむ彼女たちの背景には美術の教科書に出てくるような名画の数々が見え隠れする。ドゥオモ(大聖堂)、ベッキオ橋、ミケランジェロのダビデ像の並ぶシニョーリア広場など、風景が丸ごと美術品のようで、さながら、イタリアの美の真髄を旅しているようである。
これが今月25日にDVD化され、自宅で見ることができる。贅沢の極みだろう。
彼女たちは、異邦人でありながらイタリアを心から愛している。
何より感激するのは、戦火の中、命がけで美しい物を守ろうとする場面である。
当時、実際に彼女たちのように美しい物を愛する人たちが必死で守ってくれたからこそ、人類の遺産とも言うべき芸術が現存しているのにちがいないのだ。愚かな人間の行為で破壊させず、死守してくれた方々に、我々は心から感謝しなければならない。
以下はネタバレになるが……。
物語の最後には、実はこの作品はゼフィレッリ監督の自伝的作品だということが明かされる。
作品中でメアリーと遊んだ“ロミオとジュリエットごっこ”は、ゼフィレッリの作品「ロミオとジュリエット」への伏線だったのだ。
ちょっとした遊び心と、しゃれっけとユーモアあふれる優しい作品に仕上がっている。
2006年08月07日
オープン・ウォーター
沖でスキューバ・ダイビングを楽しんでいた夫婦が、海面に上がってみると、そこに待っているはずのツアーボートの姿が消えていた。
陸は見えず、助けが来る気配もない。水深18メートルの海に取り残された二人に、鮫の群れが近づいてくる……。
この「オープン・ウォーター」は、制作費が50万ドルに満たない低予算映画ながら、全米で3000万ドルを超す興行収入を記録したらしい。
映画に登場する鮫は、すべて本物。
出演者もスタントは一切使わず、鎖でできた防護服を身につけた役者が、鮫との“共演”に体当たりで挑んだとのこと。
鮫の訓練士も撮影に参加しているらしいが、何はともあれ無茶には違いない。
だが、だからこその臨場感、緊迫感にあふれている。
物語の着想は、1998年、オーストラリアで実際に起こった事件から。
鮫の映画といえばスティーブン・スピルバーグ監督の「ジョーズ」だが、本作の主役はあくまで人間。
人間関係の微妙な機微や、自然に対する傲慢さ。それを鮫を通して見透かしていく。
陸は見えず、助けが来る気配もない。水深18メートルの海に取り残された二人に、鮫の群れが近づいてくる……。
この「オープン・ウォーター」は、制作費が50万ドルに満たない低予算映画ながら、全米で3000万ドルを超す興行収入を記録したらしい。
映画に登場する鮫は、すべて本物。
出演者もスタントは一切使わず、鎖でできた防護服を身につけた役者が、鮫との“共演”に体当たりで挑んだとのこと。
鮫の訓練士も撮影に参加しているらしいが、何はともあれ無茶には違いない。
だが、だからこその臨場感、緊迫感にあふれている。
物語の着想は、1998年、オーストラリアで実際に起こった事件から。
鮫の映画といえばスティーブン・スピルバーグ監督の「ジョーズ」だが、本作の主役はあくまで人間。
人間関係の微妙な機微や、自然に対する傲慢さ。それを鮫を通して見透かしていく。
2006年08月05日
エニイギブンサンデー
「プラトーン」と「7月4日に生まれて」で、2度のアカデミー賞を受賞しているオリバー・ストーン監督作品。
アメリカの3大スポーツのひとつ、アメリカンフットボールを題材に、アメフトファンはもちろん、スポーツは好きだけどアメフトのルールはわからないという人も、スポーツにあまり興味がない人も、女性でも男性でも十分楽しめる仕上がりになっている。
プロフットボールチーム「マイアミ・シャークス」は、以前はチーム優勝を果たすほどの実力があったが、今では連敗、観客数も落ち込んでいる。
そんな中、ベテランのクオーターバック(デニス・クエイド)がけがをしてしまう。
ヘッドコーチであるトニー(アル・パチーノ)は、控えのウィリー(ジェイミー・フォックス)を出場させることにした。
彼ははじめこそ怖じ気づいていたが、次第に活躍するようになってくる。しかしスタンドプレーも目立ち始める。若きチームオーナー、クリスティーナ(キャメロン・ディアス)は、フットボールをビジネスとしてしかとらえておらず、若手や人気者を起用しベテランたちをはずしていこうとする。
果たして「シャークス」は再生できるのだろうか……。
アメリカでのフットボールに対する熱狂ぶりはたいへんなもので、活躍する選手は国民的スターであり、彼らには人気と同時に富と名誉がついてくる。
しかし、そうなるためには過酷な試合を勝ち続けなければならない。
迫力ある画面から、選手たちの野獣のような身体がぶつかりあい、きしむ音が聞こえてくるようだ。汗が飛び散り怒鳴り声をあげるさまはエネルギッシュそのもの。まさに男の戦場といえる。
アル・パチーノ演じるコーチには哲学がある。
ただ勝てればいいと言うわけではなく、チーム全員がひとつになって一歩でも前に進もうとすることが大切だというのだ。
こうした男臭いストーリーもさることながら、より楽しませてくれるのがフットボール史に残る伝説のプレーヤーたちが大挙して出演していることである。
さらに、映像と音楽で魅力が倍加する。
今回が初の長編となるミュージックビデオ界のサルバトーレ・トチーノの斬新な映像センスをミクスチャーロックとヒップホップの最新サウンドが彩る。 これぞエンターテインメントの極み、と言った感じだ。
アメリカの3大スポーツのひとつ、アメリカンフットボールを題材に、アメフトファンはもちろん、スポーツは好きだけどアメフトのルールはわからないという人も、スポーツにあまり興味がない人も、女性でも男性でも十分楽しめる仕上がりになっている。
プロフットボールチーム「マイアミ・シャークス」は、以前はチーム優勝を果たすほどの実力があったが、今では連敗、観客数も落ち込んでいる。
そんな中、ベテランのクオーターバック(デニス・クエイド)がけがをしてしまう。
ヘッドコーチであるトニー(アル・パチーノ)は、控えのウィリー(ジェイミー・フォックス)を出場させることにした。
彼ははじめこそ怖じ気づいていたが、次第に活躍するようになってくる。しかしスタンドプレーも目立ち始める。若きチームオーナー、クリスティーナ(キャメロン・ディアス)は、フットボールをビジネスとしてしかとらえておらず、若手や人気者を起用しベテランたちをはずしていこうとする。
果たして「シャークス」は再生できるのだろうか……。
アメリカでのフットボールに対する熱狂ぶりはたいへんなもので、活躍する選手は国民的スターであり、彼らには人気と同時に富と名誉がついてくる。
しかし、そうなるためには過酷な試合を勝ち続けなければならない。
迫力ある画面から、選手たちの野獣のような身体がぶつかりあい、きしむ音が聞こえてくるようだ。汗が飛び散り怒鳴り声をあげるさまはエネルギッシュそのもの。まさに男の戦場といえる。
アル・パチーノ演じるコーチには哲学がある。
ただ勝てればいいと言うわけではなく、チーム全員がひとつになって一歩でも前に進もうとすることが大切だというのだ。
こうした男臭いストーリーもさることながら、より楽しませてくれるのがフットボール史に残る伝説のプレーヤーたちが大挙して出演していることである。
さらに、映像と音楽で魅力が倍加する。
今回が初の長編となるミュージックビデオ界のサルバトーレ・トチーノの斬新な映像センスをミクスチャーロックとヒップホップの最新サウンドが彩る。 これぞエンターテインメントの極み、と言った感じだ。
2006年08月04日
EPISODE1-01「大統領と側近たち」ザ・ホワイトハウス<ファースト・シーズン>
記念すべきザ・ホワイトハウス<ファースト・シーズン>の第1話(PILOT)。オリジナル放映日は1999年9月22日。
当初このドラマは、広報部次長のサム・シーボーン(ロブ・ロウ)を中心に、ホワイトハウスのスタッフたちに焦点を当てたものになるはずだった。だからバートレット大統領は数回に一度程度の出演予定だったらしい。
アメリカのテレビドラマのシステムとして、まずパイロット版的な第1話を制作して放映し、その視聴率によって継続かどうかが決まる。場合によっては、あっという間に打ち切りになるわけだ。
そのためか、今話では大統領が登場場面は少ないながら大活躍している。
そして結果としてサムへの焦点は薄れ、大統領を中心としてアメリカ政治の中枢であるホワイトハウスのスタッフ全員の描写へとシフトしていく。
【ザ・ホワイトハウス<ファースト・シーズン> 第1話「大統領と側近たち」あらすじ】
第1話「大統領と側近たち」あらすじ】
電話やポケットベルで次々と呼び出される登場人物達。
「POTUS(ポータス)が自転車事故。至急、オフィスへ来い」
その中の1人、サム・シーボーン(ロブ・ロウ)は、昨晩出会った黒髪の美女ローリーの部屋でシャワーを浴びていた。
自分の物と間違えて見てしまったローリーからポケベルの内容を聞かされ、急に「残念だけど、行かなくちゃいけないんだ」と身支度を整え始める。
「友達に“変な名前ね”って言っといて。それと“お大事に”って」
「友達じゃなく上司だし、名前じゃなく肩書きなんだ」
「POTUSが?」
「大統領(President Of The United States)のことなんだ」
ジェド・バートレット大統領(マーティン・シーン)が自転車で木にぶつかり、足を怪我したのだ。
報道官のCJ・クレッグ(アリソン・ジャニー)は、マスコミへの発表に頭を痛める。
サムはポケベルの入れ違いから、ローリーが高級コールガールであることを知る。その上、生徒をホワイトハウス見学に連れてきた教師で、レオ・マクギャリー首席補佐官(ジョン・スペンサー)の娘マロリー・オブライアンに「夕べ知らずにコールガールと寝てしまった」と漏らしてしまう。
マイアミの沖では、キューバ人たちがアメリカへの亡命を望んで漂い、メディア対策の専門家であるマンディー・ハンプトンは新しい事務所を開設した。
そんな諸々の動向の一方、次席補佐官であるジョシュ・ライマン(ブラッドリー・ウィットフォード)は、テレビ番組でキリスト教右派のメアリー・マーシュに対して「あなたの崇める神さまは、脱税でお忙しい」と発言。同派の怒りをかって解雇の危機に直面していた。
広報部長のトビー・ジーグラーは、同派の首脳であるアル・コールドウェル、ジョン・バン・ダイク、そしてメアリー・マーシュとの会見をセッティング。参加を拒否するジョシュに「本来なら広報的立場から“君を首にして追い出すのが一番だ”と大統領に言うべきなんだ!……話し合いに出ろ。謝って、ここに残れ」と訴える。
しかしその会見の席上、同派のメアリーは謝罪だけでなく政治的な償いを求めてくる。その上、ユダヤ人への差別ともとれる発言に及び、ユダヤ系のトビーが激怒。謝罪による事態の収拾など無理かと思われた。
そこに杖をついたバートレット大統領が登場。
少女雑誌で中絶の権利について語った孫娘アニーにキリスト教右派の過激団体「神の子羊」から、のどにナイフの刺さった人形が届けられた事実を突きつけ、同派の首脳であるアルたちにその団体を「糾弾しろ。公然とだぞ」と返り討ちに。「それが済むまでは、ホワイトハウスに足を踏み入れることは許さん」と追い出してしまう。
今回既に、後の名コンビのやり取りが見て取れる。
ドナ「あのネクタイでテレビに出たのは失敗ね」
ジョシュ「別にネクタイのせいで、しくじったわけじゃ…」
ドナ「私が何度も止めたのに」
ジョシュ「それ何?」
ドナ「コーヒーよ」
ジョシュ「やっぱり…」
ドナ「持ってきてあげたの」
ジョシュ「何かあるんだろ?」
ドナ「別に何も」
ジョシュ「いつから僕の下で働いてる?」
ドナ「ん~…選挙中から」
ジョシュ「僕の秘書になって何年?」
ドナ「1年半」
ジョシュ「いままでコーヒーを持ってきたことあったっけ?」
ドナ「……」
ジョシュ「ないだろ? 一度だってないんだよ!」
ジョシュとドナは、最初からジョシュとドナだったんだねぇ。
トビー「君を救う手立てが、一つだけあるんだ。でも誤解しないでくれ。私は君のことが好きなわけじゃない」
この素直じゃないところがトビーらしいし、その後の思いあふれる説得もまたトビー。
レオ「他には?」
CJ「それと…」
レオ「ジョシュのことは、聞かんでくれ」
CJ「でもあなたは…」
レオ「私にも分からんのだ」
CJ「ご存知のはずです」
レオ「知らんよ」
CJ「大統領の意向を」
レオ「彼とは知り合って40年になるが、これだけは言える。彼がどんな選択をするかは、まったく予想不可能だよ」
CJ「確かに」
相手の言葉に被せるようなスピーディーな掛け合いは、この作品の魅力の一つ。
大統領「海軍によれば今朝、およそ1200のキューバ人がハバナを出発。うち700名が天候不良のため引き返し、350名が行方不明もしくは死亡、137名がマイアミに着いて保護され、亡命を望んでいる」
「背中に荷物を背負って嵐を越え、命の危険も顧みず、夢を抱いてこの国に来る。これこそ感動的だ」
「言えることは一つ。仕事に戻ろう」
大統領からスタッフ達に語りかける言葉も軽妙かつ示唆的だ。
当初このドラマは、広報部次長のサム・シーボーン(ロブ・ロウ)を中心に、ホワイトハウスのスタッフたちに焦点を当てたものになるはずだった。だからバートレット大統領は数回に一度程度の出演予定だったらしい。
アメリカのテレビドラマのシステムとして、まずパイロット版的な第1話を制作して放映し、その視聴率によって継続かどうかが決まる。場合によっては、あっという間に打ち切りになるわけだ。
そのためか、今話では大統領が登場場面は少ないながら大活躍している。
そして結果としてサムへの焦点は薄れ、大統領を中心としてアメリカ政治の中枢であるホワイトハウスのスタッフ全員の描写へとシフトしていく。
【ザ・ホワイトハウス<ファースト・シーズン>
電話やポケットベルで次々と呼び出される登場人物達。
「POTUS(ポータス)が自転車事故。至急、オフィスへ来い」
その中の1人、サム・シーボーン(ロブ・ロウ)は、昨晩出会った黒髪の美女ローリーの部屋でシャワーを浴びていた。
自分の物と間違えて見てしまったローリーからポケベルの内容を聞かされ、急に「残念だけど、行かなくちゃいけないんだ」と身支度を整え始める。
「友達に“変な名前ね”って言っといて。それと“お大事に”って」
「友達じゃなく上司だし、名前じゃなく肩書きなんだ」
「POTUSが?」
「大統領(President Of The United States)のことなんだ」
ジェド・バートレット大統領(マーティン・シーン)が自転車で木にぶつかり、足を怪我したのだ。
報道官のCJ・クレッグ(アリソン・ジャニー)は、マスコミへの発表に頭を痛める。
サムはポケベルの入れ違いから、ローリーが高級コールガールであることを知る。その上、生徒をホワイトハウス見学に連れてきた教師で、レオ・マクギャリー首席補佐官(ジョン・スペンサー)の娘マロリー・オブライアンに「夕べ知らずにコールガールと寝てしまった」と漏らしてしまう。
マイアミの沖では、キューバ人たちがアメリカへの亡命を望んで漂い、メディア対策の専門家であるマンディー・ハンプトンは新しい事務所を開設した。
そんな諸々の動向の一方、次席補佐官であるジョシュ・ライマン(ブラッドリー・ウィットフォード)は、テレビ番組でキリスト教右派のメアリー・マーシュに対して「あなたの崇める神さまは、脱税でお忙しい」と発言。同派の怒りをかって解雇の危機に直面していた。
広報部長のトビー・ジーグラーは、同派の首脳であるアル・コールドウェル、ジョン・バン・ダイク、そしてメアリー・マーシュとの会見をセッティング。参加を拒否するジョシュに「本来なら広報的立場から“君を首にして追い出すのが一番だ”と大統領に言うべきなんだ!……話し合いに出ろ。謝って、ここに残れ」と訴える。
しかしその会見の席上、同派のメアリーは謝罪だけでなく政治的な償いを求めてくる。その上、ユダヤ人への差別ともとれる発言に及び、ユダヤ系のトビーが激怒。謝罪による事態の収拾など無理かと思われた。
そこに杖をついたバートレット大統領が登場。
少女雑誌で中絶の権利について語った孫娘アニーにキリスト教右派の過激団体「神の子羊」から、のどにナイフの刺さった人形が届けられた事実を突きつけ、同派の首脳であるアルたちにその団体を「糾弾しろ。公然とだぞ」と返り討ちに。「それが済むまでは、ホワイトハウスに足を踏み入れることは許さん」と追い出してしまう。
今回既に、後の名コンビのやり取りが見て取れる。
ドナ「あのネクタイでテレビに出たのは失敗ね」
ジョシュ「別にネクタイのせいで、しくじったわけじゃ…」
ドナ「私が何度も止めたのに」
ジョシュ「それ何?」
ドナ「コーヒーよ」
ジョシュ「やっぱり…」
ドナ「持ってきてあげたの」
ジョシュ「何かあるんだろ?」
ドナ「別に何も」
ジョシュ「いつから僕の下で働いてる?」
ドナ「ん~…選挙中から」
ジョシュ「僕の秘書になって何年?」
ドナ「1年半」
ジョシュ「いままでコーヒーを持ってきたことあったっけ?」
ドナ「……」
ジョシュ「ないだろ? 一度だってないんだよ!」
ジョシュとドナは、最初からジョシュとドナだったんだねぇ。
トビー「君を救う手立てが、一つだけあるんだ。でも誤解しないでくれ。私は君のことが好きなわけじゃない」
この素直じゃないところがトビーらしいし、その後の思いあふれる説得もまたトビー。
レオ「他には?」
CJ「それと…」
レオ「ジョシュのことは、聞かんでくれ」
CJ「でもあなたは…」
レオ「私にも分からんのだ」
CJ「ご存知のはずです」
レオ「知らんよ」
CJ「大統領の意向を」
レオ「彼とは知り合って40年になるが、これだけは言える。彼がどんな選択をするかは、まったく予想不可能だよ」
CJ「確かに」
相手の言葉に被せるようなスピーディーな掛け合いは、この作品の魅力の一つ。
大統領「海軍によれば今朝、およそ1200のキューバ人がハバナを出発。うち700名が天候不良のため引き返し、350名が行方不明もしくは死亡、137名がマイアミに着いて保護され、亡命を望んでいる」
「背中に荷物を背負って嵐を越え、命の危険も顧みず、夢を抱いてこの国に来る。これこそ感動的だ」
「言えることは一つ。仕事に戻ろう」
大統領からスタッフ達に語りかける言葉も軽妙かつ示唆的だ。
2006年08月03日
ザ・ビーチ
イギリスの新進作家アレックス・ガーランドが1996年に発表したベストセラー小説「ビーチ」の映画化。
同じく若者を中心に熱狂的人気を集めるサブカルチャー系小説を映画化した「トレインスポッティング」で脚光を浴びた監督のダニー・ボイルと脚本のジョン・ホッジほかのチームを再結集させ、「タイタニック」で世界的なトップスターとしての地位を揺るぎないものにしたレオナルド・ディカプリオを主演に据え、かなりの意気込みで撮影に臨んだ本作。
さて結果はどうか?
若者が大人になるプロセスで経験する、魅惑的ではあるが危険な香りにも富んだ通過儀礼の物語――内容についていえば、そう要約できるだろう。
ディカプリオ演じるリチャードがタイのバンコクに到着する場面からストーリーは始動する。
リチャードは欧米からアジアを訪れる若きバックパッカーの典型で、これまでのイギリスでの日常的生活に飽き飽きし、自分がこのままただの大人としてダラダラした日々に埋没してしまうことへの危機感に苛まれている。
つまり治安も悪く、決して清潔ではなく、また文化的価値観も180度異なる場所にわざわざ赴く貧乏旅行は、彼自身の人生観をも180度変えてくれるような出来事や光景との出会いへの渇望を意味するのだ。
この映画でいえば、その西欧的価値観を180度変える決定的な光景を象徴するのが、伝説的な“ビーチ”の存在だ。
リチャードは偶然出会った不可解な男から、観光客の餌食になってリゾート化されることを避けるために一部の人間を除いて秘密とされている美しいビーチの存在を知らされ、地図も手にいれる。
早速リチャードは同じホテルに滞在していた同世代のフランス人カップルを誘って、旅立つ。
目的地にたどり着いた3人が目撃したのは、まさに楽園のような美しさで広がるビーチとそこで小さなコミュニティーを形作って暮らす欧米人たちの姿だった……。
前半のユートピア的な展開と比較して、後半は重苦しいムードに包まれ始める。
コミュニティーが幾つかの出来事を経て、次第に崩壊の兆しを見せ始める。
“アジアの神秘”に一方的な救済を求めがちな西欧のカウンターカルチャーが60年代末から70年代にかけて経験した挫折、コミューン幻想の崩壊を反復するかのように。
自分を変える何かを他者に求める西欧の傲慢さが裁かれるといってもいい。
つまりこの映画は十分教訓的だが、そうした部分が正直、ハリウッド大作に観客が求めるエンターテインメントの要素との間で有機的な共存にまで到達していない、とも感じられたのが残念。
同じく若者を中心に熱狂的人気を集めるサブカルチャー系小説を映画化した「トレインスポッティング」で脚光を浴びた監督のダニー・ボイルと脚本のジョン・ホッジほかのチームを再結集させ、「タイタニック」で世界的なトップスターとしての地位を揺るぎないものにしたレオナルド・ディカプリオを主演に据え、かなりの意気込みで撮影に臨んだ本作。
さて結果はどうか?
若者が大人になるプロセスで経験する、魅惑的ではあるが危険な香りにも富んだ通過儀礼の物語――内容についていえば、そう要約できるだろう。
ディカプリオ演じるリチャードがタイのバンコクに到着する場面からストーリーは始動する。
リチャードは欧米からアジアを訪れる若きバックパッカーの典型で、これまでのイギリスでの日常的生活に飽き飽きし、自分がこのままただの大人としてダラダラした日々に埋没してしまうことへの危機感に苛まれている。
つまり治安も悪く、決して清潔ではなく、また文化的価値観も180度異なる場所にわざわざ赴く貧乏旅行は、彼自身の人生観をも180度変えてくれるような出来事や光景との出会いへの渇望を意味するのだ。
この映画でいえば、その西欧的価値観を180度変える決定的な光景を象徴するのが、伝説的な“ビーチ”の存在だ。
リチャードは偶然出会った不可解な男から、観光客の餌食になってリゾート化されることを避けるために一部の人間を除いて秘密とされている美しいビーチの存在を知らされ、地図も手にいれる。
早速リチャードは同じホテルに滞在していた同世代のフランス人カップルを誘って、旅立つ。
目的地にたどり着いた3人が目撃したのは、まさに楽園のような美しさで広がるビーチとそこで小さなコミュニティーを形作って暮らす欧米人たちの姿だった……。
前半のユートピア的な展開と比較して、後半は重苦しいムードに包まれ始める。
コミュニティーが幾つかの出来事を経て、次第に崩壊の兆しを見せ始める。
“アジアの神秘”に一方的な救済を求めがちな西欧のカウンターカルチャーが60年代末から70年代にかけて経験した挫折、コミューン幻想の崩壊を反復するかのように。
自分を変える何かを他者に求める西欧の傲慢さが裁かれるといってもいい。
つまりこの映画は十分教訓的だが、そうした部分が正直、ハリウッド大作に観客が求めるエンターテインメントの要素との間で有機的な共存にまで到達していない、とも感じられたのが残念。
2006年08月02日
グリーンマイル
改めてスティーヴン・キングは、並外れた才能を持つストーリー・テラーだと実感する。
「シャイニング」で、膝がふるえるほどの恐ろしさを味わわせ、「スタンド・バイ・ミー」で、少年たちの揺れ動く心を描き、「ショーシャンクの空に」で過酷な状況の中でも夢と希望を持つことがいかに大切かを教えてくれた。
その彼の原作を新たに映画化したのが「グリーンマイル」である。
時は今から70年前、アメリカが大恐慌のころ。
ポール・エッジコム(トム・ハンクス)は、黒人差別激しい南部の刑務所で看守長をしていた。そこに、2人の少女を殺した罪でジョン・コーフィ(マイケル・クラーク・ダンカン)という死刑囚がやってくる。
泣き虫で暗闇を怖がる黒人の大男は、とても大罪を犯せるようには見えない。違和感を覚えるポールの周りに、次々に不思議な出来事が起こり始める。
コーフィは、人の心の中を感じ取り、いやすことができ、病を解き放つ奇跡を起こす力を持っているのだ。果たして、神の使いのようなこの男に殺人が犯せたのだろうか?
トム・ハンクスの押さえた演技、同じ看守仲間のデヴィッド・モースの優しさあふれる人柄、マイケル・クラーク・ダンカンの純粋で清らかな心、憎んでも憎みきれない悪役を演じるダグ・ハッチソン、心安らぐ瞬間を演じるネズミのミスタージングルズ、どれもこれもがピタッとはまり役だ。
物語は私たちに訴えかける。
なぜ、こんなに心やさしい人物を死刑という名の下に殺さなくてはならないのか。死刑制度への疑問、人種差別への怒り、人間だれもが持っている本質的な邪悪さを感じなくてはならない悲しい運命、そして、それらすべてを忘れさせ、夢を与えてくれる映画という存在の素晴らしさ――さまざまな思いが見るものの心を去来する。
「シャイニング」で、膝がふるえるほどの恐ろしさを味わわせ、「スタンド・バイ・ミー」で、少年たちの揺れ動く心を描き、「ショーシャンクの空に」で過酷な状況の中でも夢と希望を持つことがいかに大切かを教えてくれた。
その彼の原作を新たに映画化したのが「グリーンマイル」である。
時は今から70年前、アメリカが大恐慌のころ。
ポール・エッジコム(トム・ハンクス)は、黒人差別激しい南部の刑務所で看守長をしていた。そこに、2人の少女を殺した罪でジョン・コーフィ(マイケル・クラーク・ダンカン)という死刑囚がやってくる。
泣き虫で暗闇を怖がる黒人の大男は、とても大罪を犯せるようには見えない。違和感を覚えるポールの周りに、次々に不思議な出来事が起こり始める。
コーフィは、人の心の中を感じ取り、いやすことができ、病を解き放つ奇跡を起こす力を持っているのだ。果たして、神の使いのようなこの男に殺人が犯せたのだろうか?
トム・ハンクスの押さえた演技、同じ看守仲間のデヴィッド・モースの優しさあふれる人柄、マイケル・クラーク・ダンカンの純粋で清らかな心、憎んでも憎みきれない悪役を演じるダグ・ハッチソン、心安らぐ瞬間を演じるネズミのミスタージングルズ、どれもこれもがピタッとはまり役だ。
物語は私たちに訴えかける。
なぜ、こんなに心やさしい人物を死刑という名の下に殺さなくてはならないのか。死刑制度への疑問、人種差別への怒り、人間だれもが持っている本質的な邪悪さを感じなくてはならない悲しい運命、そして、それらすべてを忘れさせ、夢を与えてくれる映画という存在の素晴らしさ――さまざまな思いが見るものの心を去来する。
2006年08月01日
ふたりのトスカーナ
原作は40年ほど前にベストセラーとなったロレンツァ・マッツェッティの自伝的小説「天が落ちてくる」。
第2次世界大戦。両親を事故で失いイタリアのトスカーナ地方に住む叔母夫妻に引き取られた幼い2人の姉妹。
戦争の影が日に日に大きくなる中で、楽しい夏の日は、ある日突然に終わりを告げた……。
美しい映像を通し、少女が見た戦争の悲劇を丹念に描いている。
第2次世界大戦。両親を事故で失いイタリアのトスカーナ地方に住む叔母夫妻に引き取られた幼い2人の姉妹。
戦争の影が日に日に大きくなる中で、楽しい夏の日は、ある日突然に終わりを告げた……。
美しい映像を通し、少女が見た戦争の悲劇を丹念に描いている。
- 最近のエントリー
-
[
 新着情報]
新着情報]
- カテゴリー
- 検索
- 最近のコメント
-
- 十五才 学校IV
- └ click the next website 11/28
- └ roxy 11/30
- └ kubah mesjid enamel 01/29
- └ kedged.rcbrevisions.com/disarm/centum.html 04/12
- └ kоnyĞ° еscоrt 12/11
- └ スーパーコピー 税関 没収 類語 02/29
- └ ktokkisa 01/18
- └ Frankflism 01/24
- └ Thomastrept 01/26
- 十五才 学校IV
- 最近のトラックバック
-
-
スナッチ
- Url
- »Bom.to
- 07/04 01:21
- http://ketofatbuster.org/
- »Www.backpageladies.com
- 07/03 23:32
- Blush Farms CBD
- »jobify.info
- 07/03 21:44
- Cheapest dedicated server
- »Cheapest dedicated server
- 02/04 22:25
- actors with the best voices
- »actors with the best voices
- 10/14 03:24
- férias sem fim
- »férias sem fim
- 03/23 09:23
- 3 bhk
- »3 bhk
- 01/10 16:58
- toda la información necesaria sobre rinoplastia
- »toda la información necesaria sobre rinoplastia
- 11/18 21:35
- Occupational Psychology
- »Occupational Psychology
- 11/05 02:01
-
スナッチ
- ブログ・アクセサリー
-
-

track feed -
-
-