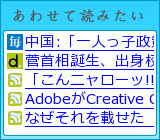自宅でDVD三昧!~映画・ドラマどんと来い!
もちろん映画館で見る大画面の映画の雰囲気は最高。でも自宅でまったりDVD三昧というのも良い物だ。人目を気にせず見た映画DVD・ドラマDVDの感想など書き散らしてみたり。
« 2006年08月22日 | メイン | 2006年08月24日 »
2006年08月23日
アンジェラの灰
1997年ピュリツァー賞を受賞し、欧米で600万部の大ベストセラーとなった同名ドキュメンタリーの映画化。
1930年代、アイルランドからの移民としてニューヨークで暮らすマコート一家。若い夫妻には4人の幼い男の子と生まれたばかりの女の子がいた。
不況で父親に仕事はなく、彼は失業手当まで呑んでしまうほどの酒好きだった。食べるものもなく、ある日、小さな女の子は死んでしまう。悲しみにくれる母親は、故郷の家族を頼ろうと、一家でアイルランドに戻る。
アイルランドに戻っても、父親は働かなかった。働いてもすぐにクビになり、失業手当は酒代に消えた。ここで、下の双子の男の子が次々に亡くなる。そして、また子どもが生まれる。父親に対して、妻も子どもたちも呆れているが、憎み突き放すことはできない。
映画を見ながら、エミール・ゾラの小説「居酒屋」を思い出した。「居酒屋」は、だんながヤクザな男だったため、娼婦にまで身をやつす女の物語である。
男にほれ、情、母性が仇となって不幸になる女性は多い。逆に、呑む、打つ、買うといった遊びにうつつをぬかし、女性や家族を不幸の泥沼に引きずり込む男も多い。
女の愚かさと男のずるさ。
これは、男と女の悪しき業ともいえるだろう。アンジェラの灰は、この業を見るものに突きつける。
やましいところのある人は、そら恐ろしい気持ちになるにちがいない。
この映画は、主人公フランクが、少年から青年へと育つ成長談である。
フランクは、どんなに悲惨な状況でも、子どもらしく伸び伸びとしている。随所に、ウイットに富んだエピソードがちりばめられており、笑いを誘う。
健康な男の子の関心といえば、異性であり、性であるが、それも牧歌的な楽しい話ばかり。また、アイルランドでは、キリスト教のカトリックの教えが徹底されているようだが、フランクの自然な発想は、カトリックの厳格な教えを説く教師たちをハッとさせたりする。
また、この映画では、社会の最底辺に暮らす庶民の生活が丹念に描かれている。街並み、食べるもの、着るもの、部屋、トイレまで、街の息づかいがこまやかに伝わってくるようだ。
庶民への温かな視点をもった作品だ。
ニューヨークでも、アイルランドでも、食べるものがないとき、近所のやさしいおばさんが助けてくれたりする。
何とも言えない郷愁を誘う作品だ。
1930年代、アイルランドからの移民としてニューヨークで暮らすマコート一家。若い夫妻には4人の幼い男の子と生まれたばかりの女の子がいた。
不況で父親に仕事はなく、彼は失業手当まで呑んでしまうほどの酒好きだった。食べるものもなく、ある日、小さな女の子は死んでしまう。悲しみにくれる母親は、故郷の家族を頼ろうと、一家でアイルランドに戻る。
アイルランドに戻っても、父親は働かなかった。働いてもすぐにクビになり、失業手当は酒代に消えた。ここで、下の双子の男の子が次々に亡くなる。そして、また子どもが生まれる。父親に対して、妻も子どもたちも呆れているが、憎み突き放すことはできない。
映画を見ながら、エミール・ゾラの小説「居酒屋」を思い出した。「居酒屋」は、だんながヤクザな男だったため、娼婦にまで身をやつす女の物語である。
男にほれ、情、母性が仇となって不幸になる女性は多い。逆に、呑む、打つ、買うといった遊びにうつつをぬかし、女性や家族を不幸の泥沼に引きずり込む男も多い。
女の愚かさと男のずるさ。
これは、男と女の悪しき業ともいえるだろう。アンジェラの灰は、この業を見るものに突きつける。
やましいところのある人は、そら恐ろしい気持ちになるにちがいない。
この映画は、主人公フランクが、少年から青年へと育つ成長談である。
フランクは、どんなに悲惨な状況でも、子どもらしく伸び伸びとしている。随所に、ウイットに富んだエピソードがちりばめられており、笑いを誘う。
健康な男の子の関心といえば、異性であり、性であるが、それも牧歌的な楽しい話ばかり。また、アイルランドでは、キリスト教のカトリックの教えが徹底されているようだが、フランクの自然な発想は、カトリックの厳格な教えを説く教師たちをハッとさせたりする。
また、この映画では、社会の最底辺に暮らす庶民の生活が丹念に描かれている。街並み、食べるもの、着るもの、部屋、トイレまで、街の息づかいがこまやかに伝わってくるようだ。
庶民への温かな視点をもった作品だ。
ニューヨークでも、アイルランドでも、食べるものがないとき、近所のやさしいおばさんが助けてくれたりする。
何とも言えない郷愁を誘う作品だ。
- カテゴリー
- 検索
- 最近のコメント
-
- 十五才 学校IV
- └ click the next website 11/28
- └ roxy 11/30
- └ kubah mesjid enamel 01/29
- └ gucci 2014 boxing day 2014 12/18
- └ kedged.rcbrevisions.com/disarm/centum.html 04/12
- └ kоnyĞ° еscоrt 12/11
- └ ktokkisa 01/18
- └ Frankflism 01/24
- └ Thomastrept 01/26
- 十五才 学校IV
- 最近のトラックバック
-
-
スナッチ
- http://www.villa-rent.com
- »Www.villa-rent.com
- 02/29 03:44
- https://consciouslifenews.com/kitty-health-care-how-often-should-you-replace-cat-litter/11182234
- »Consciouslifenews.com
- 02/29 01:25
- The Complete Remote Viewing Training System By Gerald O'donnell
- »prima-ballett.de
- 02/29 01:10
- Cheapest dedicated server
- »Cheapest dedicated server
- 02/04 22:25
- actors with the best voices
- »actors with the best voices
- 10/14 03:24
- férias sem fim
- »férias sem fim
- 03/23 09:23
- 3 bhk
- »3 bhk
- 01/10 16:58
- toda la información necesaria sobre rinoplastia
- »toda la información necesaria sobre rinoplastia
- 11/18 21:35
- Occupational Psychology
- »Occupational Psychology
- 11/05 02:01
-
スナッチ
- ブログ・アクセサリー
-
-

track feed -
-
-