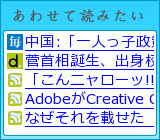自宅でDVD三昧!~映画・ドラマどんと来い!
もちろん映画館で見る大画面の映画の雰囲気は最高。でも自宅でまったりDVD三昧というのも良い物だ。人目を気にせず見た映画DVD・ドラマDVDの感想など書き散らしてみたり。
« 2006年07月26日 | メイン | 2006年07月28日 »
2006年07月27日
博士の愛した数式
交通事故の後遺症で、天才数学者の博士(寺尾聰)は、記憶がたった80分しかもたない。何を話していいか混乱した時、言葉の代わりに数字を持ち出す。
相手を敬う心を忘れず、常に数学のそばから離れようとしない。そんな、いささか風変わりな博士のもとで働くことになったシングルマザーの家政婦・杏子(深津絵里)。その10歳の息子(齋藤隆成)を、博士は、“ルート(√)”と呼ぶ。博士と語り合ううち、二人は数式の中に秘められた、美しい意味を知る――。
芥川賞作家・小川洋子のベストセラーとなった同名小説を、『雨あがる』の小泉堯史監督が映画化した。
この映画には、数学への憧憬や、数字の美しさへの心酔がちりばめられている。
ごく普通の人からみれば、数学者の振る舞いや、数字に意味を見いだそうとする行為は、奇異に思えるものだ。あまりにも純粋に率直に示される、博士の数学への深い愛情が、家政婦とその息子にも、だんだんとうつっていく様子がみてとれる。80分ごとに記憶をなくす博士は、常に相手を初対面として接する。けれど、そこには人としての佇まいの美しさがある。
原作の面白さ、魅力をあまねく引き出しながら、また違った、映画ならではの世界を構築している。主だった登場人物は、たった5人。長じて、数学教師となった“ルート”を演じる吉岡秀隆と、浅丘ルリ子を加えた5人の役者たちは、どの一人が欠けても、均衡が崩れるかのような、絶妙な緊張感で存在する。
数学になぞらえていうならば、それぞれが素数の美しさ(!)を保ちながら、互いに慕わしさをかもしだしている。
相手を敬う心を忘れず、常に数学のそばから離れようとしない。そんな、いささか風変わりな博士のもとで働くことになったシングルマザーの家政婦・杏子(深津絵里)。その10歳の息子(齋藤隆成)を、博士は、“ルート(√)”と呼ぶ。博士と語り合ううち、二人は数式の中に秘められた、美しい意味を知る――。
芥川賞作家・小川洋子のベストセラーとなった同名小説を、『雨あがる』の小泉堯史監督が映画化した。
この映画には、数学への憧憬や、数字の美しさへの心酔がちりばめられている。
ごく普通の人からみれば、数学者の振る舞いや、数字に意味を見いだそうとする行為は、奇異に思えるものだ。あまりにも純粋に率直に示される、博士の数学への深い愛情が、家政婦とその息子にも、だんだんとうつっていく様子がみてとれる。80分ごとに記憶をなくす博士は、常に相手を初対面として接する。けれど、そこには人としての佇まいの美しさがある。
原作の面白さ、魅力をあまねく引き出しながら、また違った、映画ならではの世界を構築している。主だった登場人物は、たった5人。長じて、数学教師となった“ルート”を演じる吉岡秀隆と、浅丘ルリ子を加えた5人の役者たちは、どの一人が欠けても、均衡が崩れるかのような、絶妙な緊張感で存在する。
数学になぞらえていうならば、それぞれが素数の美しさ(!)を保ちながら、互いに慕わしさをかもしだしている。
草ぶきの学校
子どもたちの純粋な瞳は、喜びも悲しみも、真正面から映し出す。
その小さな胸に、大人以上の葛藤の嵐が吹くこともある。
決して楽しさだけじゃなかった、けれども幸せだった子ども時代――。
1962年ごろ、文化革命前の中国農村部に暮らした子どもたちを描いた作品。砂にまみれ、風に吹かれて育まれた、懐かしい日々が思い起こされる。
友情、家族愛など、少年の視線から見た日常が鮮やか。
戦後の日本とも重なるノスタルジィで、地味ながら爽やかに浸らせてくれる。
その小さな胸に、大人以上の葛藤の嵐が吹くこともある。
決して楽しさだけじゃなかった、けれども幸せだった子ども時代――。
1962年ごろ、文化革命前の中国農村部に暮らした子どもたちを描いた作品。砂にまみれ、風に吹かれて育まれた、懐かしい日々が思い起こされる。
友情、家族愛など、少年の視線から見た日常が鮮やか。
戦後の日本とも重なるノスタルジィで、地味ながら爽やかに浸らせてくれる。
- カテゴリー
- 検索
- 最近のコメント
-
- 十五才 学校IV
- └ click the next website 11/28
- └ roxy 11/30
- └ kubah mesjid enamel 01/29
- └ timberland earthkeepers fit 12/04
- └ gucci 2014 boxing day 2014 12/18
- └ kedged.rcbrevisions.com/disarm/centum.html 04/12
- └ Men's Air Max 87 12/17
- └ Nike Shox Deliver Scarpe 12/19
- └ read this 09/08
- 十五才 学校IV
- 最近のトラックバック
-
-
ジャンヌ・ダルク
- 2016年全国老板手机号码大全
- »2016年全国老板手机号码大全
- 09/11 11:50
- mobitrans android
- »mobitrans android
- 02/11 07:33
- facebook.com/Getbuyvenusfactortrial-1111094645567977/
- »facebook.com/Getbuyvenusfactortrial-1111094645567977/
- 01/30 02:15
- Rebelution concert Tv
- »125.209.197.98
- 09/11 11:49
- Dustin lynch tickets prince edward island
- »www.telpacindustriesinc.com
- 09/11 10:53
- Thuốc mọc râu nào tốt và tìm mua chúng ở đâu?
- »thuocmocraure.blogspot.com
- 09/11 09:41
- 北京电加热器
- »心里发问难道是一中的学生服务员们围坐在一
- 09/09 03:07
- 摇臂裁断机温度控制系统
- »轮胎硫化罐温度控制机
- 09/04 01:06
- 卧式导热油加热器
- »电水加热器
- 09/04 01:05
-
ジャンヌ・ダルク
- ブログ・アクセサリー
-
-

track feed -
-
-